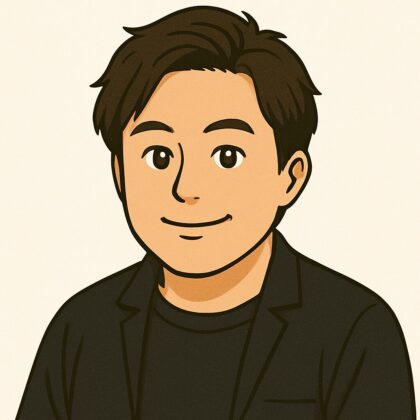物語を観る映画ではない、という前提から始めたい
この映画を語るうえで、まずはっきりさせておきたいことがある。
『大統領の料理人』は、物語の起伏やドラマ性を期待して観る作品ではない。
感情を強く揺さぶる展開もなければ、胸を打つ名セリフが連発されるわけでもない。だがその代わりに、この映画はとても静かで、丁寧で、そして不思議なほど心地いい時間を与えてくれる。
大統領の料理人は、観るというより「味わう」という言葉のほうがしっくりくる映画だ。
あらすじ|田舎の料理人がエリゼ宮殿へ招かれるまで
フランスの田舎で小さなレストランを営んでいた女性料理人オルタンス。
ある日突然、彼女のもとに政府の公用車が現れ、パリのエリゼ宮殿へと招かれる。理由はただひとつ、フランソワ・ミッテラン大統領のプライベートシェフとして料理を作ってほしいという依頼だった。
名誉ある大役である一方、彼女を待っていたのは男社会の厨房と、女性料理人というだけで向けられる冷たい視線だった。オルタンスは歓迎される存在ではなく、最初から「よそ者」として扱われる。しかし本作は、その葛藤を大きな衝突や劇的な対立として描こうとはしない。
エリゼ宮殿の厨房に漂う、驚くほど静かな空気

エリゼ宮殿と聞けば、政治や権力、張り詰めた空気を想像する人も多いだろう。だがこの映画が映し出すのは、そうしたイメージとは真逆の世界だ。
厨房に流れるのは、包丁の音や鍋の湯気、食材に向き合う料理人の呼吸だけ。政治的な駆け引きは背景に退き、画面の中心にあるのは「料理を作る」という行為そのものだ。そこには過剰な説明も演出もなく、ただ淡々と、誠実に料理が作られていく。
ごとに伝わってくる。その積み重ねが、「これはきっと美味しいに違いない」という確信を生み、観る者の五感を刺激してくる。
料理がすべてを持っていく映画体験

正直に言えば、ストーリーを細かく追おうとすると集中力は途切れがちになる。だが、その代わりに視線は自然と料理へと引き寄せられる。
作中に登場する料理は、どれも派手ではない。見たこともない料理ばかりだが、不思議と難解さはなく、ただ「美味しそうだ」という感覚だけが残る。食材の扱い方、盛り付けの緊張感、完成した瞬間の静かな達成感。その一つひとつが積み重なり、気づけば物語よりも料理の余韻のほうが記憶に残っている。
料理に興味がある人やグルメな人にとっては、間違いなく刺さる映画だろう。だが料理に詳しくなくても問題はない。必要なのは、美味しいものを見るのが好きだという感覚だけだ。
内容重視派には、やはり物足りない
この映画の弱点もまた明確だ。ドラマとしての起伏は控えめで、カタルシスはほとんどない。人物関係の変化も控えめで、明確な「盛り上がりどころ」を期待すると肩透かしを食らう。
そのため、内容重視の人や、強いメッセージ性を求める人には物足りなく映るだろう。この評価は決して間違っていない。
それでも、この映画が記憶に残る理由
それでも『大統領の料理人』は、観終わったあとに不思議な余韻を残す。理由は単純で、この映画が一貫して「料理を作ることそのものの幸福」を描いているからだ。
誰かに勝つためでもなく、評価を得るためでもない。ただ美味しいものを誠実に作る。その姿勢が、観る側の心を静かにほどいていく。派手な感動はないが、生活の温度が少し上がるような感覚だけが残る。
休日の午後にこそ似合う一本
この映画は、忙しい平日の夜に気合を入れて観る作品ではない。少し時間に余裕のある休日の午後、コーヒーやワインを片手に、流すように観てほしい。集中して理解する映画ではなく、ゆっくり味わう映画だからだ。
評価表(2014年7月時点)
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| ストーリー | ★★☆☆☆ |
| 演技 | ★★★☆☆ |
| 映像美 | ★★★★☆ |
| 料理描写 | ★★★★★ |
| 総合評価 | 61点/100点 |
総評コメント
物語としては控えめだが、料理描写の魅力だけで最後まで観せ切る一本。派手さはないが、嫌いになれない映画である。

大統領の料理人
片田舎で小さなレストランを営むオルタンス・ラボリがスカウトを受け、連れて来られた新しい勤務先はエリゼ宮。そこはなんとフランス大統領官邸のプライベートキッチンだった。堅苦しいメニューと規律と縛られた食事スタイル、嫉妬うずまく官邸料理人たちの中で、彼女が作り出すのは「美味しい」の本当の意味を追求した料理の数々。