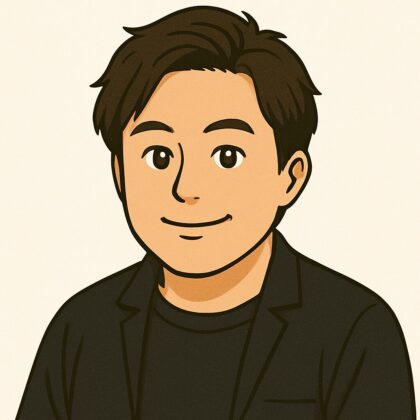The SALOVERS 2月22日発売シングル。
20歳という“刹那”を刻んだ一曲
2012年にリリースされた The SALOVERS の「ディタラトゥエンティ」は、20歳という年齢にしか宿らない 痛み・焦燥・希望 を、そのまま音にしたような楽曲だ。
タイトルの「ディタラ」は造語で、“チャラい雰囲気を持つ音”としてつけられたもの。
そこに「トゥエンティ(twenty=20)」を掛け合わせた言葉遊びが、軽薄さと真剣さがせめぎ合う20歳の心象をそのまま映している。

リリースは 2012年2月22日。
当時のメンバーは全員が20歳前後であり、まさに「今の自分たち」を作品に封じ込めた。
ライブ会場とタワーレコード限定という形式も、商業性よりも“等身大の衝動”を優先した若いバンドらしい選択だった。
歌詞に宿るテーマ:無垢から大人へ、痛みの中の成長
「ディタラトゥエンティ」の歌詞を聴いてまず心を掴まれるのは、
冒頭の一節──
「男を知らない汚れなき処女たちよ」
挑発的にも聞こえるこのフレーズは、“まだ何も知らない純粋さ”へのまなざしでもある。
それは決して嘲笑ではなく、むしろ 憧憬と哀しみを含んだ眼差しだ。
「自ら血を流して大人になっては」
という一節が象徴するのは、成長が痛みを伴うものであるという現実。
大人になることは、誰かに教わることではなく、自らの傷を引き受けて変わっていく過程なのだ。
若さの不安と衝動:モラトリアムの真ん中で
曲の中盤で印象的なのが、
「死にたくないとか生きてゆけないとか 若き日によくこぼしたあの口癖」
というライン。
誰もが一度は抱く “どう生きていいかわからない”という不安。
それを、飾らず、かといって安易に慰めることもなく歌い上げている。
そして次のフレーズ──
「愛に溺れてく気分はどうだい」
ここには、恋や情熱に翻弄される20歳の危うさがある。
自己嫌悪と開き直りの狭間で揺れる感情。
その生々しさが、聴く者の胸を刺す。
絶望の向こうにある希望──救いのラスト
この曲がただの“痛みの歌”で終わらないのは、
ラストに差し込まれる次の一節の存在だ。
「いつの日か誰かの心を癒すでしょう
そしてまた新たに生きる歓びを知るのでしょう」
ここには、絶望を越えた先にある希望が見える。
傷つきながらも、誰かを癒せる日が来る。
その未来を信じるわずかな光が、曲全体の陰影をやわらげ、“青春の救い”として響く。
バンドのリアル:20歳の自分たちを刻む音

リリース当時、The SALOVERSのメンバーはまさに「20歳」そのものだった。
作詞・作曲を手がけた 古舘佑太郎 は、
自身の等身大の焦燥や迷いを隠すことなく詞に投影している。
彼の声には、不安と希望、孤独と連帯が同時に宿る。
その震えは、完璧さよりもむしろ“未完成の美しさ”を感じさせる。
のちに古舘が俳優として活動を広げ、バンドが活動休止・再始動を経験していく中でも、この曲は「あの頃のままの純度」を保ち続けている。
“今”を切り取ったからこそ、時を経ても色あせないのだ。
「ディタラトゥエンティ」が青春アンセムである理由
この曲が多くのリスナーにとって“青春アンセム”として響くのは、単に若さを歌ったからではない。
そこにあるのは、生きることの矛盾そのものだ。
20歳は、大人でも子どもでもない曖昧な時間。
社会と自分の間で迷いながら、それでも前に進もうとする瞬間。
「ディタラトゥエンティ」は、その瞬間の不安・眩しさ・痛みをそのまま刻んでいる。
そして今、30代や40代になったリスナーがこの曲を聴き返すと、あの頃の自分に「それでも生きていける」と語りかけたくなる。
それこそが、この曲が時を超えて輝き続ける理由だ。
痛みの中でしか見えない光
The SALOVERSの「ディタラトゥエンティ」は、若さゆえの痛みを“否定”ではなく“肯定”として描いた作品だ。
どんなに傷ついても、その痛みがやがて他人を癒す力に変わる。
それは20歳の彼らが信じた、そして今を生きる私たちにも必要な 希望のかたち だ。
この曲を聴くたびに、あの頃の不器用な自分がふと顔を出す。
「それでも大丈夫」とそっと背中を押してくれる。
──そんな力を持った、永遠の青春ソングである。
気軽に投稿して下さい♪