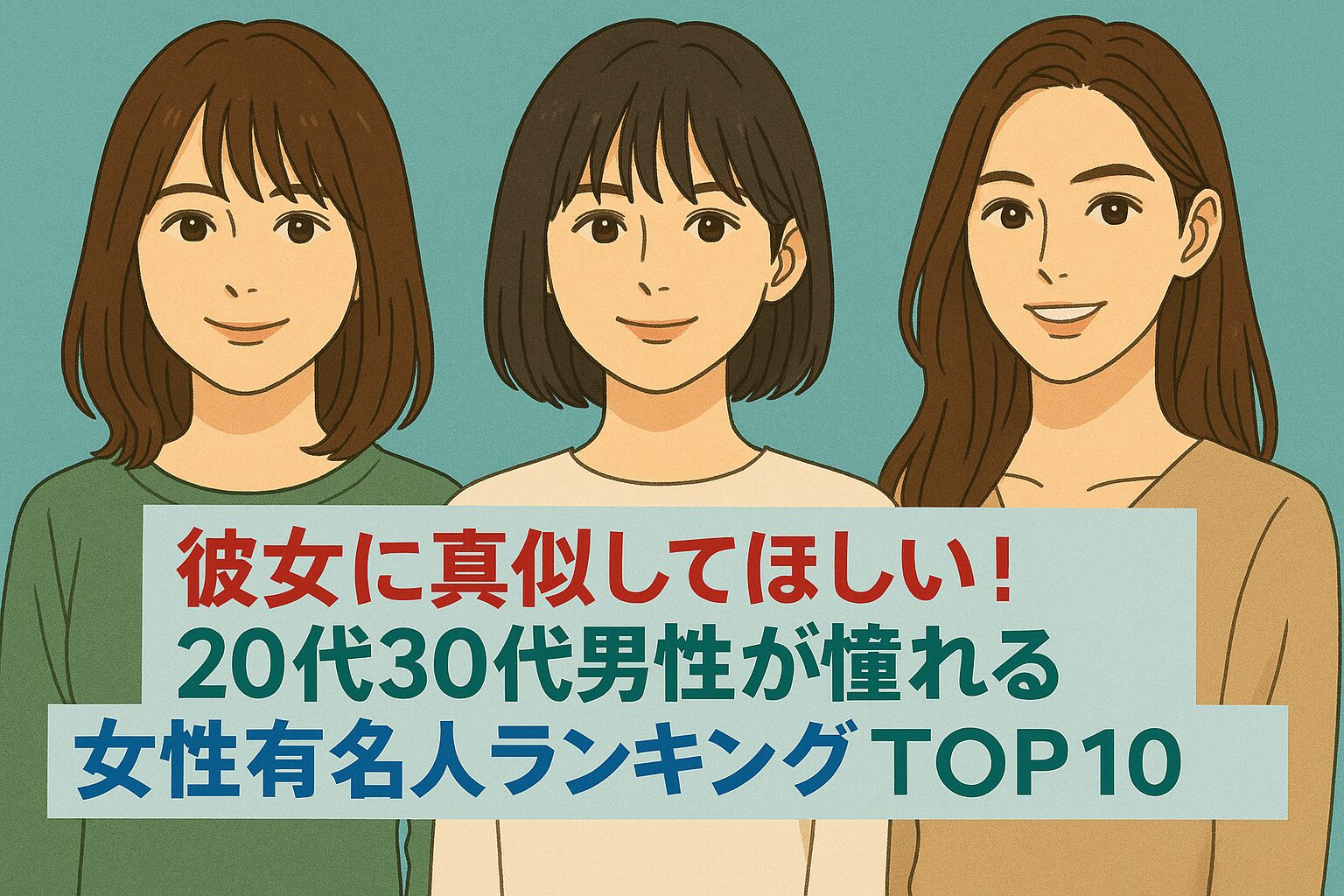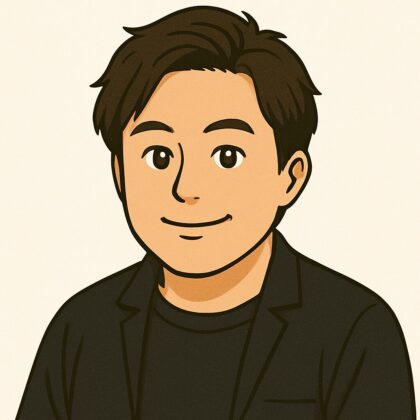感情を抱えたまま闘う男、日下部峻
フジテレビ系火曜21時ドラマ『新東京水上警察』で、加藤シゲアキが演じる日下部峻は、警視庁捜査一課から突然“新東京水上警察署”に異動となった刑事だ。
捜査一課といえば警察内部でも花形部署。周囲から“エリート”と評されていた日下部にとって、この異動は屈辱に近い。
加藤は、この「プライドと焦燥」を絶妙なバランスで体現する。
表情のわずかな揺れ、言葉の間、怒りを飲み込む瞬間――それらが日下部という人物を“単なる熱血刑事”に留まらせない。
同僚の碇拓真(佐藤隆太)に対しては、嫉妬・尊敬・反発といった複雑な感情を交錯させながらも、事件と真摯に向き合う。
密かに交際している海技職員・礼子(山下美月)に不器用な愛情を見せる場面では、人間としての弱さが露わになる。
公式サイトの人物紹介には「“直感派”の碇とは水と油の関係」とあるが、だからこそ彼らの成長過程は物語の大きな軸だ。
第1話からすでに、碇と日下部の間には衝突と信頼の予兆が見え隠れする。
加藤はその関係性を、怒りや焦りの中に“まだ言葉にならない変化”として演じ切っている。
近年の役柄が映す“人間の揺らぎ”

加藤の近年の出演作を振り返ると、共通して見えてくるキーワードがある――「揺れ」だ。
『連続ドラマW シャイロックの子供たち』(WOWOW)では、平穏な家庭を持つ銀行員が抱える秘密を静かに滲ませた。
『六畳間のピアノマン』(NHK)では、パワハラ上司の下で葛藤する新入社員の不安と再生を丁寧に描いた。
『満天のゴール』(NHK BS4K)では、海辺の診療所で働く医師として、過去のしがらみを背負いながら前に進もうとする姿を見せた。
『あきない世傳 金と銀』(NHK BS)では、商才を持つ次男・幸之助として、家業を継ぐ野心と家族への葛藤を両立。
『連続ドラマW 夜がどれほど暗くても』(WOWOW)では、記者として“正義とは何か”に葛藤する青年を演じ、理想と現実の狭間で成長していく姿を見せた。
いずれの役にも「理想と現実」「正義と打算」「憧れと嫉妬」といった二面性が存在する。
その繊細な心の綾を、加藤は声を荒げることなく、眼差しや沈黙で描く。
まるで“光と影が同時に呼吸する”ような演技。それが彼の真骨頂だ。
小説家としての言葉、役者としての身体
2012年、小説『ピンクとグレー』でデビューした加藤は、作家としても第一線で活躍を続けている。
以降、『閃光スクランブル』『Burn.-バーン-』『傘をもたない蟻たちは』『なれのはて』と、作品ごとに文体とテーマを刷新。
2023年には『なれのはて』で直木賞候補に選出され、文学界でも確固たる地位を築いた。
2025年刊行の最新作『ミアキス・シンフォニー』では、“喪失の先にある希望”を7年かけて描き上げた。
インタビューでは、「書くことは自分を観察する行為」と語り、役者としての“他者を演じる”行為と対比させている。
作家業と俳優業――一見異なる表現のようでいて、その根底に流れるテーマは共通している。
「人間の中にある“矛盾”を見つめ、そこから光を探す」こと。
日下部という役柄にも、その哲学が色濃く映っている。
音楽と舞台、そして“構築する”表現者へ
NEWSのメンバーとしての活動も、加藤の表現の重要な一部だ。
作詞・作曲に携わりながら、ライブ構成や演出にも関与する。
その視点は、単なる“パフォーマー”ではなく、“空間を設計する人”に近い。
2025年にはテレビ朝日主催の音楽イベント『S-POP LIVE』でライブファシリテーターを務め、アーティストと観客を“感情でつなぐ役割”を担うことが発表された。
また、短編映画祭『SSFF & ASIA 2025』で特別賞を受賞するなど、映像制作への関心も広がっている。
演じる、書く、歌う、創る――そのいずれもが“表現”という一本の軸で結ばれている。
彼の活動を俯瞰すれば、「ジャンルを超える」というより、「ジャンルそのものを溶かしている」と言った方が正確だろう。
「全部お芝居だと思ってる」──その言葉の真意
俳優・中尾明慶のYouTubeチャンネルに出演した際、加藤はこう語った。
「作家もアイドルも役者も、全部お芝居だと思ってる。」
この言葉は、彼の表現哲学を象徴している。
“お芝居”とは、単に誰かになりきることではない。
他者の視点に立ち、異なる人生を想像し、そこにリアリティを吹き込む行為。
それは執筆にも、音楽にも、ステージにも共通する。
そしていま、『新東京水上警察』の日下部峻として、加藤シゲアキはその哲学を現実に体現している。
感情を抱えたまま、それでも前に進もうとする姿に、彼自身の“生き方”が重なる。
「作ること」と「演じること」を往復する時間

近年、加藤がメディアでしばしば口にするのが、「インプットとアウトプットの往復」という言葉だ。
小説を書くとき、彼は長時間ひとりで考え、世界を構築する。
だが、演じるときは、他者とぶつかり合いながら感情を交換する。
この往復運動が、彼の作品群を独自の温度にしている。
書くことで人間の構造を理解し、演じることでその構造に“血”を通わせる。
どちらも欠けると、加藤シゲアキという表現者は成立しない。
音楽活動もその延長線上にある。
NEWSのステージでは、観客の呼吸を読み取り、物語を再構築するようにライブを紡ぐ。
そこに“加藤らしさ”が宿るのは、彼が舞台を「一夜限りの小説」として見ているからだ。
彼にとって表現とは、世界を理解するための方法であり、同時に「生き延びるための術」でもある。
そんな加藤が今後どんな表現に挑むのか――小説の新作、ドラマの続編、舞台演出、あるいはまったく新しいメディアかもしれない。
いずれにしても、その根底に流れるのはただひとつ。
「人間とは、感情を持つ存在だ」という真実。
それを多角的に描き出すことこそ、2025年の加藤シゲアキが目指す“その先”なのだ。
その先にあるもの
表現者としての加藤シゲアキは、すでに“俳優”や“作家”という枠を超えている。
ひとりの人間が、言葉・音・身体・映像を媒介に“感情”を世界に伝える存在――
それが、彼の現在地だ。
日下部峻がこれからどんな成長を見せるのか。
そして加藤シゲアキが、この先どんな新しい“表現の形”を提示していくのか。
その両方から、目が離せない。