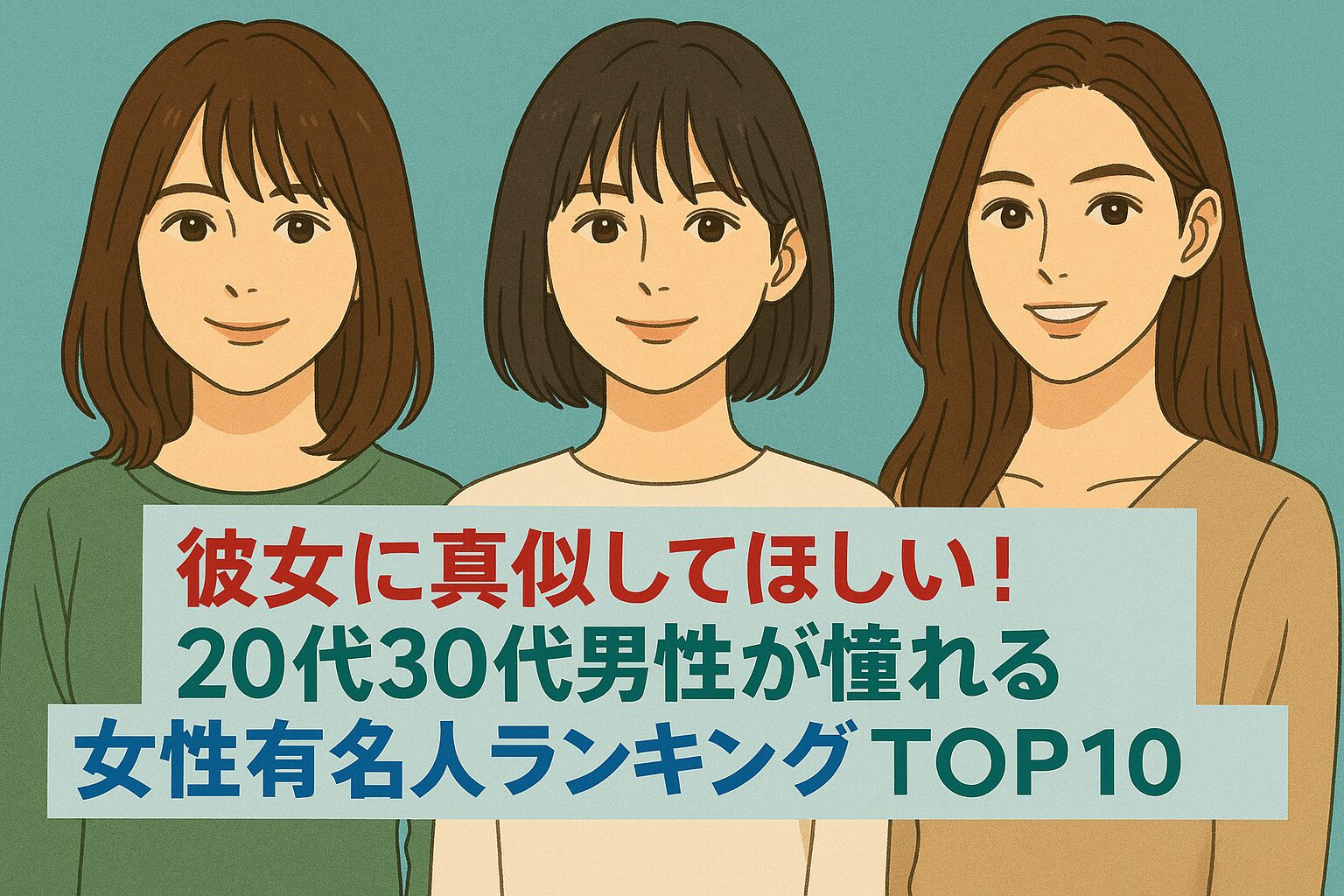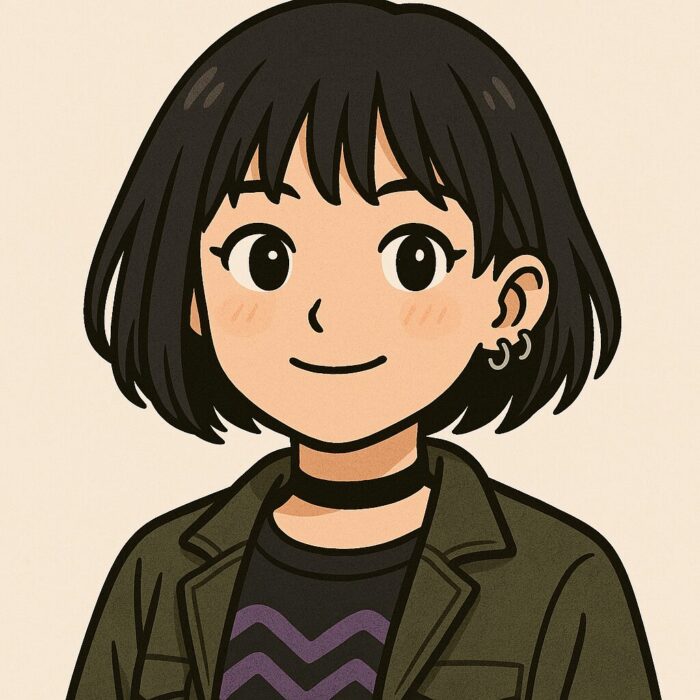『僕達はまだその星の校則を知らない』──その挑戦的なタイトルを初めて見たとき、多くの人がこう感じたのではないだろうか。「え、どういう意味?」と。だが第1話を観たあとには、むしろこう問い返される。「あなたは、"校則"の意味を本当に理解していますか?」と。
見知らぬ宇宙に迷い込むように始まる第1話
舞台は共学になったばかりの濱ソラリス高校。生徒会長と副会長が学校に来なくなった理由も、校内に漂う閉塞感も、何かがおかしい。そこに突然現れるのが、スクールロイヤー・白鳥健治(磯村勇斗)だ。
彼は、「生徒の味方」なのか、それとも「学校の手先」なのか。第1話の大半で、その立ち位置が曖昧なまま物語が進んでいく。この“掴ませなさ”こそが、このドラマの魅力であり、真骨頂でもある。
学校という「小宇宙」に巣食う構造的な違和感
ドラマはただの学園ものではない。むしろ、「学園ドラマ」というラベルが似合わないほどの静謐さと深さがある。
特に象徴的なのが、模擬裁判のシーン。正義や理想を学ぶ場であるはずのそれが、実態は“力と服従”の儀式になっていた。そのことに違和感を抱く生徒は少数派で、むしろ「ルールを破ったのが悪い」とする空気が支配している。
これは単なるフィクションではない。現実の学校や職場、社会にも蔓延する「空気に従うことが正解」という構造をあぶり出している。
磯村勇斗演じる白鳥健治の“拒絶と共鳴”
白鳥は、学校を「太陽系外宇宙勢力」になぞらえる。そう口にすることで、彼自身が“学校”にトラウマを抱えていることがほのめかされる。
しかし、彼はその拒絶のなかで、生徒たちのまなざしの真っすぐさに心を打たれていく。中でも、生徒同士の“連帯”の瞬間は胸を打つ。対立していた鷹野と瑞穂が、互いの本音を言葉にするシーンは、正解のない問いに、自分なりの答えを出す勇気そのものだった。
言葉よりも、余白が語る──音楽と演出の力
この作品を支えているもう一つの魅力が、フランス人作曲家ベンジャミン・ベドゥサックによる劇伴。主張しすぎない旋律が、心の揺れを静かにすくい上げる。
場面ごとの“間”の取り方や、過剰に説明しない演出も、視聴者に「考える余地」を残してくれる。ドラマに引き込まれるというより、“自分の内面と向き合わされる”感覚になる。
『校則』は誰を守り、誰を縛っているのか
第1話の終盤、校則の是非を議論するのではなく、「今、それがどう機能しているか?」という視点に移った瞬間、世界が反転する。ルールの目的とは、秩序の維持か、誰かの支配か、それとも安心のためか。
そしてこの問いに、明確な答えは提示されない。提示されるのは、問いかける勇気と、考え続ける余白だけだ。
🔍 スクールロイヤーという存在が照らす教育現場の“グレーゾーン”

「スクールロイヤー」とは、現実にも一部自治体が導入を進めている制度で、学校と法的アドバイザーとの連携によって、いじめ、校則、トラブルの対処を透明化しようとする取り組みだ。
しかし、実際の教育現場において、法と現場感覚は必ずしも一致しない。教師と生徒、生徒と親、学校と地域社会──それぞれの正義がぶつかる場所で、法の視点は「中立の知恵」として機能するのか?
本作は、ただ「法律で解決しよう」という単純な物語ではない。むしろ、「法律でさえ割り切れない問題が、学校には山ほどある」と示しているのだ。
この視点こそが、日本の教育現場が直面している“変化の予兆”なのかもしれない。
🎬 その校則、本当に必要ですか?
『僕達はまだその星の校則を知らない』第1話は、派手な展開はない。けれど、静かに、確実に、あなたの中に問いを置いていく。
「なぜそれを守るのか?」
「なぜそれに従わなければならないのか?」
そして――「本当にそれが、誰かのためになっているのか?」
次回の展開も気になるが、まずはこの第1話を、もう一度じっくりと見返してみてほしい。あなた自身の“校則”を、問い直すために。