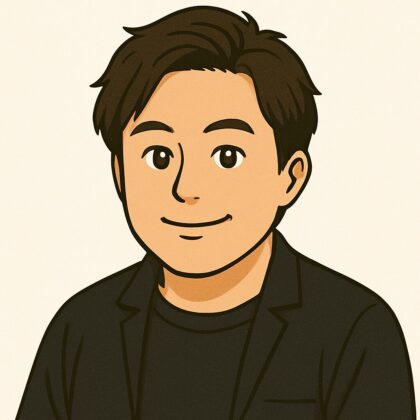寒さが本格的になり、街のざわめきが少しずつ静まっていく12月。一年を振り返りながら、温かい物語を求めたとき、自然と思い出してしまう作品がある。
「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」だ。
大きな事件が起きるわけでも、派手な展開が続くわけでもない。それでも、年末が近づくと「もう一度読みたい」と感じさせる力が、この作品には確かにある。本稿では、その理由を丁寧にひも解いていきたい。
人付き合いを拒んでいた小説家と、世話焼きな猫
主人公・朏素晴(みかづき・すばる)は、人との関わりを極力避けて生きるミステリー作家だ。
本と空想の世界だけが安心できる居場所で、他人との会話は必要最低限。担当編集者とのやり取りすら苦痛で、過去には偏屈な態度が原因で編集者が体調を崩してしまったこともある。
そんな素晴の生活が変わるきっかけとなったのが、偶然出会った一匹の野良猫だった。
創作の資料になるかもしれない。そんな打算から始まった同居生活は、当然のように思い通りにはいかない。
猫は人の生活リズムなど考慮しない。鳴く、荒らす、勝手に甘える。
素晴は混乱し、振り回され、苛立ちながらも、少しずつ外の世界へ引き出されていく。
この作品を特別なものにしている「猫の視点」

本作の最大の特徴は、同じ出来事が人間側と猫側、2つの視点で描かれる構造にある。
素晴編では、「猫あるある」に右往左往する人間の滑稽さが描かれる。
しかし、その直後に描かれるハル編では、まったく異なる物語が立ち上がる。
餌を何度も運ぶ行為は、気まぐれではなく心配から。
仏壇を荒らしたように見えた行動も、ハルなりの“守ろうとする意識”だった。
人間が「困った行動」だと思っていたものが、猫にとっては必死の選択だったと知る。その瞬間、読者は自分自身の思い込みに気づかされる。
この視点のズレこそが、本作を単なる癒やし漫画で終わらせない最大の要因だ。
広がっていくのは、人の世界だけではない
ハルを迎え入れたことで、素晴の人間関係は少しずつ広がっていく。
ペットショップの店員・押守、友人の大翔、その家族、近隣の住人たち。猫を通じて生まれた関係は、無理のない距離感で素晴の生活に入り込んでくる。
一方で、ハルの世界もまた広がっていく。
病院で出会った猫、野良時代の仲間、隣家の犬、そして生き別れた弟との再会。
この作品が優しいのは、「誰かの世界が広がること」を決して劇的に描かない点だ。
日常の延長線上で、静かに、確実に変化が積み重なっていく。
年末に刺さるのは、「後悔」と「守りたい」という感情
ハルは、守れなかった過去を持つ猫だ。
弟を失った記憶、冷たくなった体の感触。その経験が、ハルの行動原理になっている。
だからこそ、食事を取らず倒れそうになる素晴が放っておけない。
ハルにとって素晴は、「守らなければならない存在」なのだ。
一方の素晴は、ハルが自分を守ろうとしているとは知らない。ただ、寄り添う温もりに救われ、孤独から少しずつ解放されていく。
年末という時期は、不思議と過去の後悔や、失ったものを思い出しやすい。
だからこそ、この2人の関係性が、普段以上に胸に響く。
読み返すたびに、違う場所で泣ける物語
初読では、猫の可愛さに癒やされる。
読み返すと、人間関係の変化に気づく。
さらに時間が経つと、「一緒にいること」そのものの尊さが浮かび上がる。
「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」は、読む側の人生の位置によって、刺さるポイントが変わる作品だ。
だからこそ、節目である年末に、もう一度手に取りたくなる。
なぜ“理解し合えなさ”が、こんなにも温かいのか
この作品は、完全な相互理解をゴールにしていない。
素晴は最後まで、ハルの本当の気持ちを正確には知らない。ハルもまた、人間の複雑な感情を完全に理解しているわけではない。
それでも、2人は共に生きる。
現実の人間関係も同じだ。
誤解はなくならない。すれ違いも起きる。それでも隣にいる。
「同居人はひざ、時々、頭のうえ。」が長く愛され続ける理由は、その不完全さを肯定してくれる点にある。
年末にこの作品を読み返す行為は、自分の一年を、そして自分自身を、そっと肯定する行為なのかもしれない。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。
ステリー作家・朏 素晴(みかづき すばる)は、自らの想像の世界を邪魔する他人が苦手。そんな素晴の元にやってきたのは、一匹の猫。その不可解な行動を見ているうちに、小説のネタが浮かんできて……!? 不器用男子×一匹の拾い猫。 ふたりでみつける幸せぐらし。人と猫、W視点で贈る物語。猫のきもちが知りたい人、必見です。