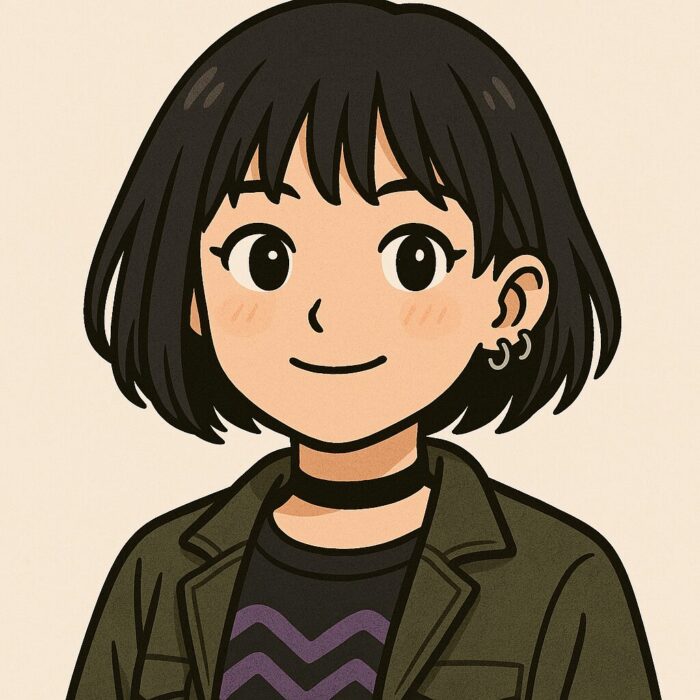1. ドラマが照らす“声なき存在”
「技能実習制度」という言葉に、どれほどのリアリティを感じるだろうか。
TBS系『イグナイト -法の無法者-』第3話は、そんな制度のもとで働く外国人実習生の“声なき声”にフォーカスを当てた回だった。表面上は“人材育成”という建前のもとに成り立つ制度が、実態としては“安価な労働力の搾取”へと変質している現実を、ドラマは巧みに描き出す。
この回では、間宮祥太朗演じる弁護士・宇崎が、制度の網に絡め取られた実習生の人生を救おうと奮闘する姿が描かれた。
2. 宇崎が選んだ“ひとりの声”を拾う決断
物語は、宇崎が事務所にひとり残される場面から始まる。そんな中、港町・帆刈町で食堂を営む高山(アンミカ)が現れ、「助けてほしい」と訴えるのは、外国人実習生・クオンの事故とその後の不可解な対応だった。
怪我をしても詳細を語ろうとしないクオンの様子に、宇崎は直感的に“何かが隠されている”と察する。そして、事務所の方針や上司の指示を無視してでも動き出す。彼の行動原理は「正義感」ではない。むしろ、自身の抱える矛盾や鬱屈を照らすかのように、弱き者のために手を伸ばすのだ。
3. 技能実習制度のリアルとドラマの交差点
技能実習制度をめぐる問題は、今や日本社会の深部に根付いた構造的な闇といえる。
労働基準法違反、賃金未払い、過酷な労働時間、安全配慮の欠如……。名目は“育成”でも、現実は“搾取”。
そうした現場で起こる事故や自殺、逃亡といった事例は、ニュースの片隅に埋もれていく。
近年のドラマでもこのテーマは注目されており、『東京サラダボウル』『ゼイチョー』『MIU404』などがそれぞれ異なる角度からこの問題を掘り下げている。『イグナイト』はそこに「弁護士」という視点を持ち込み、法の正義が必ずしも人の正義と重ならないことを描いた。
4. 弁護士ができること、できないこと
作中で伊野尾(上白石萌歌)はこう語る。
「法を知ることは、声を出せるっていうこと。知らないと、何も言えないのと同じ」
このセリフは、単なる台詞以上の重みを持つ。
言葉を持たない、あるいは持っていても“通じない”環境に置かれた実習生たち。
彼らが直面するのは、法的知識の不足ではなく、“制度に参加する権利”そのものの欠如である。
弁護士である宇崎たちの仕事は、「起きてしまった事件」にしか対応できない。
未然に救えないもどかしさは、視聴者の胸にも重くのしかかる。
5. “首輪”の比喩が映し出す二重の抑圧構造
今話では、宇崎自身も“首輪”をつけられた存在として描かれる。
過去に事務所の代表・轟(仲村トオル)が、宇崎の実家の借金を肩代わりしたことで、彼は自由を奪われている。
一見すると全く異なる境遇にあるようで、宇崎とクオンには**共通する“支配される構造”**がある。
異なるのは、それを噛みちぎる気力と、逃げ場の有無だけだ。
6. 制度改革は救いになるのか
裁判の終盤、宇崎は技能実習制度が「育成就労制度」へと見直される流れに言及する。
だが、それは本当に“救済”と言えるのか?
制度の名前が変わっても、構造的な搾取や管理の仕組みがそのままであれば、また同じような事件は繰り返される。
クオンのような若者が“育成”の名の下に傷つく未来が防げるとは限らない。
宇崎の口から出る「願うことしかできない」という言葉は、私たちが直面すべき現実そのものだ。
7. まとめ:物語から見えてくる現実の輪郭
『イグナイト』第3話は、単なる“事件解決ドラマ”ではない。
それは社会に埋もれた「見ないふりができる問題」を、観る者の目の前に突きつける挑戦的な作品だ。
技能実習制度という社会的問題を、ただの題材ではなく“人間ドラマ”として描いた本作。
登場人物たちの選択は、現実社会の私たちに「どう向き合うのか?」という問いを返してくる。
8. 現実の技能実習制度は今どうなっているのか?
2024年、日本政府は長年の問題が指摘されていた外国人技能実習制度を見直し、新たに「育成就労制度」へと移行する方針を発表しました。
◾️ 主な変更点:
転職の自由度が一定程度認められる
職場環境改善の監視体制を強化
悪質企業への罰則強化
一見前向きな変化に見えるが、実態としては“名を変えた同じ構造”が温存されているという懸念の声も多い。現場の声を拾わないまま制度改革が進めば、また新たな形の“沈黙”が生まれることになる。
「育成」という名にふさわしい制度となるには、労働者の声が制度設計の中心になければならない。
その視点を忘れたとき、制度は再び“搾取の装置”に戻ってしまうだろう。
『イグナイト』はフィクションでありながら、現実に警鐘を鳴らすリアルなメッセージを内包している。
“声なき声”に耳を傾けること。それが、社会を変える第一歩なのかもしれない。