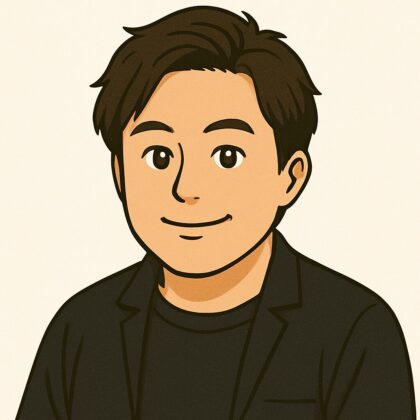はじめに──なぜ今、「こんなこいるかな」なのか?
2026年3月、NHK Eテレの長寿番組 おかあさんといっしょ の中で、ひとつのアニメが40年ぶりに復活します。作品名は**『こんなこいるかな』**。
1986年から約5年間放送され、絵本シリーズは累計1000万部を突破。多くの家庭で親しまれたショートアニメが、令和の時代に再び動き出します。
しかしこの復活は、単なる“懐かしコンテンツの再利用”ではありません。本作は、1980年代に提示された「子ども観」を、現代に問い直す存在でもあります。
『こんなこいるかな』とはどんな作品だったのか
1986年に放送開始。1話完結のショートアニメとして『おかあさんといっしょ』内で展開されました。
登場するのは、個性豊かな12人の子どもたち。


・「いやだいやだ」と主張する“やだもん”
・こわがりやの“ぶるる”
など、それぞれの性格そのものがキャラクター名になっています。
ここで特筆すべきは、彼らが“直される対象”ではなかったことです。
当時の子ども向け作品の多くは、「困った行動 → 反省 → 改善」という流れを取る構造が主流でした。
しかし『こんなこいるかな』は違います。
「こんな子もいるよね」それだけで物語が成立する。
善悪で分けない。優劣をつけない。12人全員が主役であり、“その他大勢”はいません。
この設計そのものが、作品の思想でした。
1980年代という時代と作品の先進性
1980年代後半、日本社会では「よい子像」が比較的明確に存在していました。
・我慢強い
・協調性がある
・素直である
そうした価値観が前提とされる時代に、「いやだ」と言う子どもを主人公に据える発想は、決して一般的ではありませんでした。
原作者である絵本作家・有賀忍は、作品に込めた思いとして次のように語っています。
「いろんな人がいるからこそ楽しい」ということを子どもたちに知ってもらいたかった。
大人には「子どものあるがままの姿」を認めてほしい。
教育的メッセージを前面に出すのではなく、日常のユーモアの中で肯定を描く。
このアプローチは、今の視点で見るとむしろ時代を先取りしていたと言えるでしょう。
2026年、新作はどう描かれるのか
2026年3月30日より、『おかあさんといっしょ』内で新作アニメとして放送が始まります。放送時間は以下の通りです。
月〜水曜 7:45〜8:10/18:00〜18:24
土曜 7:45〜8:10/17:00〜17:24
制作方針は、「オリジナルの魅力を大切にしながら、現代の子どもたちに親しみやすい表現で描く」というもの。
ここで鍵になるのが、“現代らしさ”です。
令和の子どもたちは、SNS文化、早期教育、情報過多の環境の中で育っています。また、「多様性」「発達特性」「自己肯定感」といった概念も社会に広く浸透しました。1986年当時は“柔らかな問題提起”だったテーマが、2026年の今は“社会的リアリティ”を持つテーマになっています。
なぜ40年後に蘇るのか
復活の理由は、大きく三つ考えられます。
1. 世代循環のタイミング
かつてこの作品を見ていた子ども世代が、今は親世代になっています。親子二世代で同じ作品を共有できる構造は、番組にとっても大きな価値です。
2. 多様性時代との親和性
現代社会は「違いを認める」ことを重視します。『こんなこいるかな』の基本思想は、この価値観と自然に接続します。
3. 短編フォーマットの強み
ショートアニメ形式は、集中時間が短い幼児層に適しています。テンポよく、わかりやすく、押しつけがましくない。
形式面でも、現代的なのです。
“肯定のお話”というコンセプトの本質
有賀忍は本作を「肯定のお話」と表現しました。
重要なのは、“無条件に甘やかす”ことではありません。
・まず存在を認める
・性格を矯正の対象にしない
・長い時間軸で見守る
この視点は、現在の子育て論や教育観とも重なります。
「良い子になること」を目標にするのではなく、「その子らしさが輝くこと」を前提にする。
12人全員が主役という構造は、その思想を最も端的に示しています。
40年の時間が変えたのは、作品か、それとも私たちか
40年という時間は、作品を変えると同時に、受け取る側も変えます。
1986年当時、『こんなこいるかな』は「ちょっと変わった優しいアニメ」だったかもしれません。しかし2026年の今、「多様性」「インクルーシブ教育」「自己肯定感」という言葉が日常語になった社会で見ると、その思想は驚くほど普遍的です。
むしろ私たち大人のほうが、かつてより“正解”を求めすぎている可能性もあります。子どもに理想像を投影し、効率的な成長を期待し、比較してしまう。
そのとき、この作品は静かに問いかけます。
「そんなに急がなくてもいいのでは?」
また、ショートアニメという形式も再評価すべきポイントです。情報過多の時代において、短い時間で完結する物語は、子どもにとっても親にとっても負担が少ない。余白があり、解釈を押しつけない。この“余白”こそが、本作の最大の価値です。
そして何より重要なのは、「全員が主役」という構造。これは単なる演出上の工夫ではありません。社会の縮図でもあります。
学校でも、家庭でも、社会でも、誰かが“その他大勢”になりがちです。しかしこの作品は、その前提を崩します。
12人全員が主役。誰一人、背景にはならない。
40年ぶりの復活は、過去の再演ではなく、今の社会に必要な視点の再提示なのかもしれません。
2026年の『こんなこいるかな』がどのような表現でその思想を描くのか。それを見届けること自体が、私たち大人への宿題と言えるでしょう。