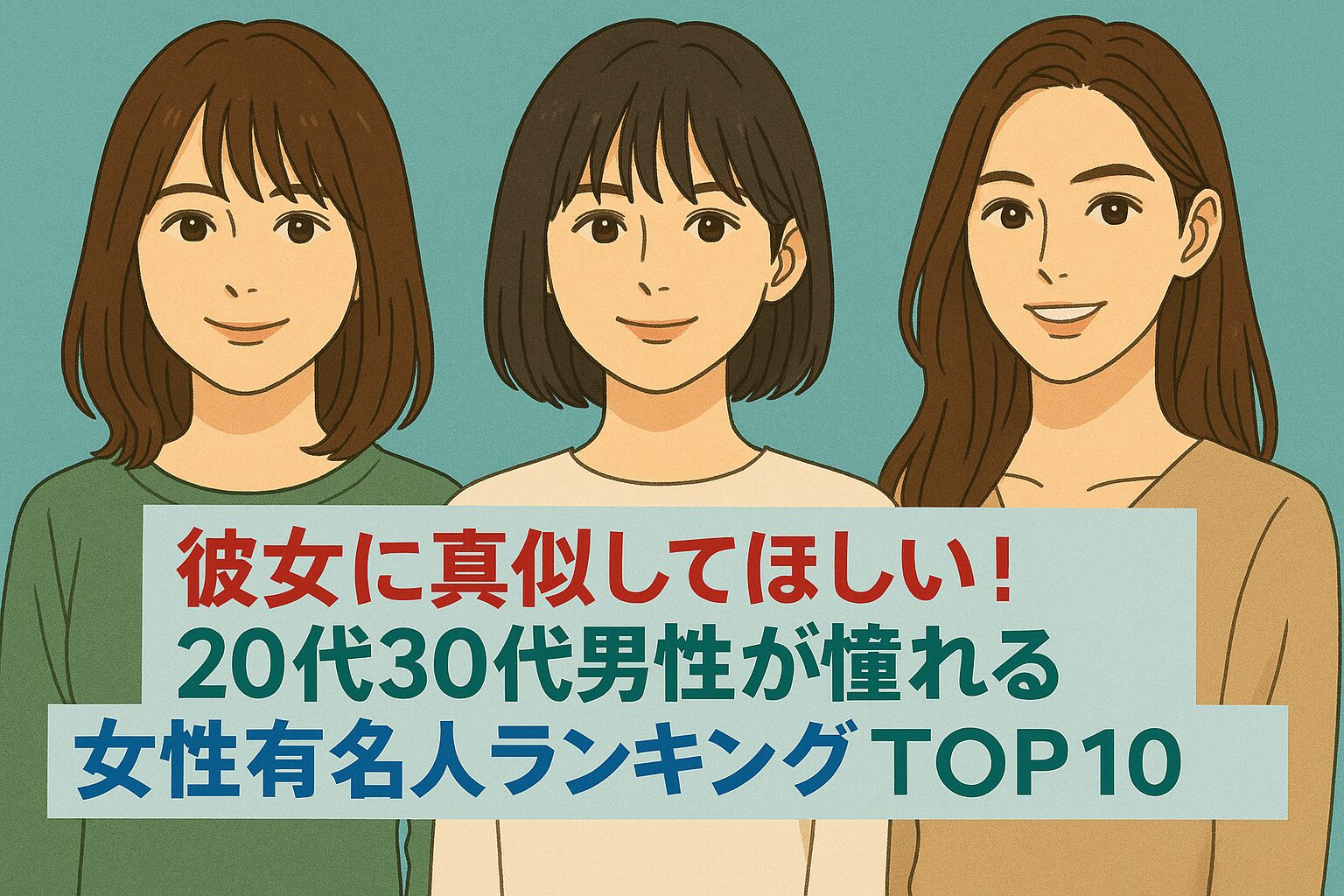「フランス発のSFアニメ映画」と聞くと、まず映像の珍しさに目が行きがちです。でも『マーズ・エクスプレス』が強いのは、そこじゃない。“世界の仕組み”が物語として走り出す瞬間の気持ちよさが、最初から最後まで途切れません。
そして今回、その芯の部分に反応したのが、磯光雄・大友克洋・小島秀夫という、説明不要の作り手たち。三者三様の褒め方なのに、指している場所がだいたい同じなのが面白いところです。
『マーズ・エクスプレス』基本情報
- 作品:『マーズ・エクスプレス』(原題:Mars Express)
- 監督:ジェレミー・ペラン(Jérémie Périn)
- 舞台:西暦2200年/火星
- 上映時間:89分
- 日本公開日:2026年1月30日(金)全国ロードショー
- 日本語吹替主要キャスト:佐古真弓(アリーヌ)、安元洋貴(カルロス)、内田夕夜(クリス)、三瓶由布子(ロベルタ)
物語の入口は「失踪事件」だが、刺さるのは“社会の歪み”

本作は、23世紀の火星で活動する私立探偵アリーヌ・ルビーと、アンドロイドの相棒カルロス・リヴェラが、ある事件の捜査に関わるところから始まります。
“事件”を追う映画の顔をしつつ、観客がじわじわ気づくのは、火星社会が抱える構造のほころびです。
ポイントはここ。
この映画、未来設定を「説明」で見せない。代わりに、捜査で訪れる場所、人々の働き方、企業の力学、ロボットの扱われ方が、そのまま世界観の説明になっている。だから観終わったあとに残るのは、「真犯人は誰?」以上に、「この社会、どこから壊れていった?」という後味です。
磯光雄が反応した“ハードSFの手触り”とは何か
磯光雄が言葉を寄せたニュースでは、作画・デザインの完成度、そして日本で最近は見かけにくい“ハードSFの遺伝子”に触れています。これを作品側から言い換えると、凄みは「設定の硬さが、絵の硬さではなく“物語の推進力”になっている」ところ。
ハードSFって、専門用語や数字を並べることじゃないんですよね。『マーズ・エクスプレス』がやっているのは、もっと映画的で、もっと嫌らしい(褒めてます)。技術が生活に溶けた世界で、どんな摩擦が起きるか。便利さの裏に、誰の権利が押しつぶされるか。そこが捜査の展開と噛み合っていて、見ている側は「理解」より先に「納得」させられる。
大友克洋が見た“BD感”は、絵柄ではなく「視線の運び」
大友克洋のコメントは、BD(バンド・デシネ)的な感覚と、日本アニメからの影響がありつつも監督独自の作品になっている点を評価する内容でした。ここで大事なのは、「フランスっぽい絵」かどうかじゃありません。
BD的というのは、むしろカメラの置き方と情報の出し方。街の成り立ち、階層、権力の匂い、生活の汚れ——そういう“背景の物語”を、説明でなく画面設計で積み上げる。結果、観客は「この世界はきっとこう動く」と自然に推測できるようになる。
この“推測できる世界”こそが、サスペンスを加速させます。犯人探しが面白いのは、世界が信用できるから。信用できるのは、絵が嘘をつかないから。そんな循環がずっと回っている感じです。
小島秀夫が反応した“80〜90年代硬派SFアニメの匂い”の正体

小島秀夫のコメントは、ルック、デザイン、世界観、物語、テーマ、作家性といった総合力が、押井守・川尻善昭・今敏らを連想させる、という方向でした。ただし、これは単なる懐古ではありません。
本作が思い出させるのは、当時の硬派SFアニメにあった、
「実写でもカートゥーンでもない」中間のリアリティ
社会と個人の距離が近い怖さ
正義が単純に勝たない後味
こういう“体温の低い熱さ”です。
『マーズ・エクスプレス』は、そこを現代の作劇でやり直している。しかも89分という尺で、過不足なく。
小島が“保護すべき”とまで言いたくなるのは、派手な盛り上げより、こういう作りが商業環境で成立しにくい現実も含んでいるのかもしれません。
吹替キャストのコメントが示す「この映画の見どころの芯」
公式発表の吹替キャストコメントを見ると、共通して出てくるのが「生活感」「実写のよう」「ロボットなのに人間臭い」といった感想です。
つまり本作は、SFのガジェットより先に、人間の面倒くささを描いている。
ロボットと共存する社会って、夢の未来の話にも、ディストピアの話にもできる。『マーズ・エクスプレス』が怖いのは、そのどっちにも寄り切らず、「まあこうなるよね」という地続きのリアルで迫ってくるところです。
タイトルの「マーズ・エクスプレス」は実在の探査機名でもある
作品名は、欧州宇宙機関(ESA)の火星探査ミッション「Mars Express」と同名。ESA公式ページでは、打ち上げ日が2003年6月2日と明記されています。
このネーミングが効いているのは、「火星=ロマン」よりも、「火星=現実の延長」の温度に寄せてくれるから。映画が描くのは、未知の星というより、植民・産業・都市生活の果てにある火星です。
『マーズ・エクスプレス』が“刺さる人”にだけ深く刺さる理由
『マーズ・エクスプレス』の面白さは、「世界観がすごい」で終わらないところにあります。世界観は確かに濃い。でも、この映画は濃さを“自慢”しない。むしろ淡々と、捜査の導線に混ぜてくる。だから観客は、設定を覚える前に、この社会の空気を吸ってしまう。吸ってしまった瞬間から、事件の謎は「物語の謎」ではなく、「社会の症状」に見えてきます。
もう一つ、刺さる理由は、ロボットの扱い方が極端じゃない点です。ロボットが可哀想だから泣け、でもない。ロボットが危険だから排除、でもない。共存が当たり前になった社会で、人間側もロボット側も、当然のように利害を持ち、嘘をつき、正当化をする。その“当然さ”が一番怖い。吹替キャストが口にする「生活感」「人間臭さ」は、まさにそこから来ているはずです。
そしてここが、磯光雄・大友克洋・小島秀夫の反応に繋がるポイントでもあります。三人がそれぞれ別の言葉で褒めているのに、共通して見えてくるのは「作りが誠実」という一点。誠実というのは、現実の仕組みをコピーするという意味ではなく、映画の中の世界が“そのルール通りに動く”ということ。ルール通りに動く世界では、登場人物の選択が重くなる。選択が重いから、サスペンスが効く。サスペンスが効くから、テーマが説教にならない。つまり本作の凄みは、思想や設定を語る前に、映画としての駆動で観客を連れていく設計にあります。
もしあなたが、派手な説明や“わかりやすい正義”に少し疲れているなら、この89分はかなり気持ちいいはずです。硬派SFの顔をして、実はものすごく娯楽として速い。そういうタイプの作品です。