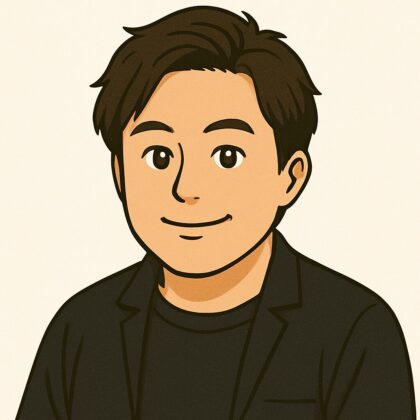2010.6.5 sapporo
あの頃、モーモールルギャバンが“刺さった”理由
2000年代後半、東京のライブハウスシーンには、奇抜で、変態で、でもどうしようもなく心に残るバンドがいた。
その名もモーモールルギャバン。
パンクともニューウェーブとも形容しがたいサウンドに、意味不明でバカらしい歌詞。だけどそこに宿るのは、まぎれもなく青春のエネルギーと哀愁だった。
今回は、彼らの代表曲の中でも特に「サイケな恋人」と「POP!烏龍ハイ!」という2曲を取り上げ、なぜこれほどまでに“当時の若者たちにブッ刺さった”のかを紐解いていく。
「サイケな恋人」:静けさから爆発する、歪んだ愛の形
2008年、自主制作盤としてリリースされた「サイケな恋人」。ギターレスの編成に移行して初めての作品として、モーモールルギャバンの新章の始まりを象徴する1曲でもある。
✔ ギターなしの異端構成が生んだ空気感
ドラム、ベース、キーボードという特異な構成。ギターがない代わりに、キーボードが泣くように、叫ぶようにメロディを紡ぐ。音の隙間に漂うのは、どこか都市の雑踏のような孤独感。
まるで、下北沢や高円寺の路地裏に漂う、夜の切なさと安っぽさが音になったような感触だ。
✔ 恋愛はこんなにもダサくて、愛おしい
歌詞には「恋愛ってバカだなあ」と言いたくなるような情けなさが満載。だけど、そのバカバカしさに、なぜか涙腺が刺激される。
ライブでは「パンティー!」と叫ぶコール&レスポンスが定番だが、そのくだらなささえも含めて、青春のどうしようもなさを全身で肯定してくれる1曲。
「POP!烏龍ハイ!」:疾走する夜、無敵のテンション

一方の「POP!烏龍ハイ!」は、2009年にリリースされたフルアルバム『野口、久津川で爆死』に収録。こちらは一転して、明るくて、軽くて、でも切ない。
✔ アルコールが彩る、夜の無敵感
タイトルからもわかるように、テーマは“酔っぱらった青春”。烏龍ハイを片手に、街をふらつく若者たちの夜の景色が浮かぶ。
速いビートに乗せて、何かから逃げるような、あるいは何も考えたくない夜の衝動が走り抜ける。意味なんてどうでもいい、今この瞬間だけが全て――そんなエモさにあふれている。
✔ 「楽しさ」と「むなしさ」が共存する名曲
POPという言葉が持つ「軽さ」。それは裏返せば儚さでもある。
キラキラした音像の中に、ふと見え隠れする「このままじゃダメだ」と気づいてしまう瞬間。都会の夜に飲み込まれていく若者の一瞬の輝きが、この曲には詰まっている。
なぜ“当時の若者”にブッ刺さったのか?
✔ シモネタなのに、泣ける。
パンティーを連呼し、変な声で絶叫する。ふざけてるようで、でも真剣に生きてる感じがした。
モーモールルギャバンの音楽は、「こんな自分でも、生きてていいのかもしれない」と思わせてくれる包容力があった。
✔ 高円寺・下北沢的“雑多感”の象徴
整っていない。スマートじゃない。
でもその不器用さにこそリアルがあった。フライヤーが貼られたライブハウス、使い古されたアンプ、タバコ臭い楽屋。
そんな風景にぴったりとハマる音楽だった。
✔ 自分の“ダサさ”を肯定してくれる音楽
「カッコいい」じゃなく、「愛おしい」。
傷ついたり、ヘラったり、意味もなく街をふらついたりする、“何者でもなかった頃”の自分たちを、彼らの音楽はまるごと肯定してくれた。
モーモールルギャバンという音楽は、“愛すべきバカ”たちの人生賛歌だった

「サイケな恋人」も「POP!烏龍ハイ!」も、どちらも笑えるほどバカで、笑えないほど切ない。
それはたぶん、人生も恋愛も、どこかそんな風にできているからだ。
もし、最近ちょっと疲れてるなら。
夜の街がちょっと寂しく見えたなら。
ぜひこの2曲を聴いてみてほしい。
パンティーと叫ぶその向こうに、あなたの青春がきっと見えるはずだ。
気軽に投稿して下さい♪