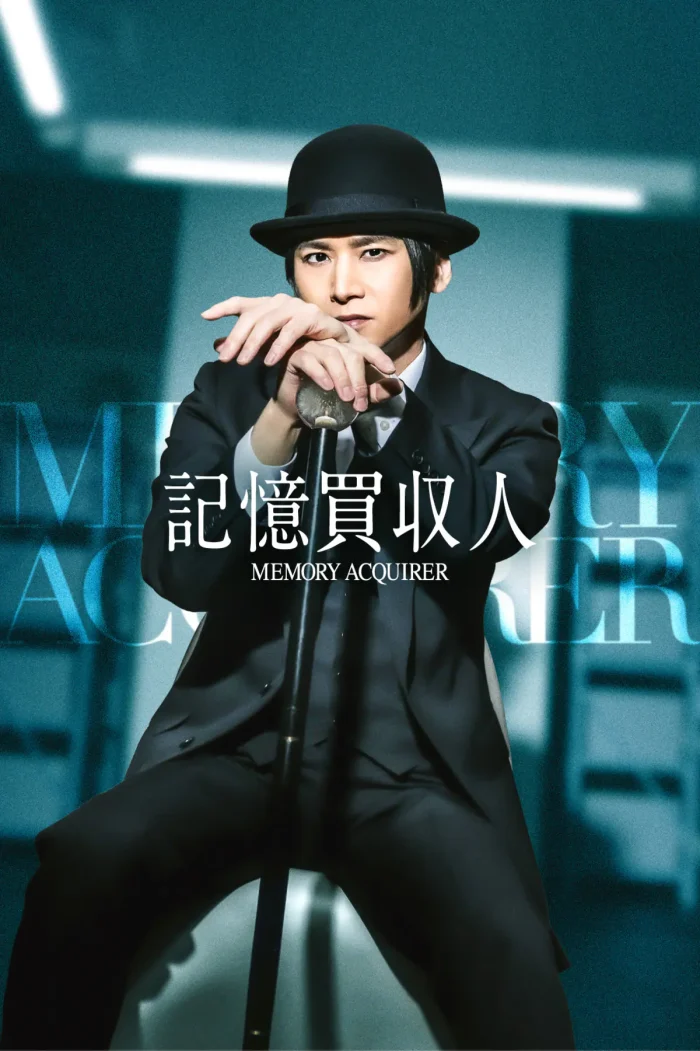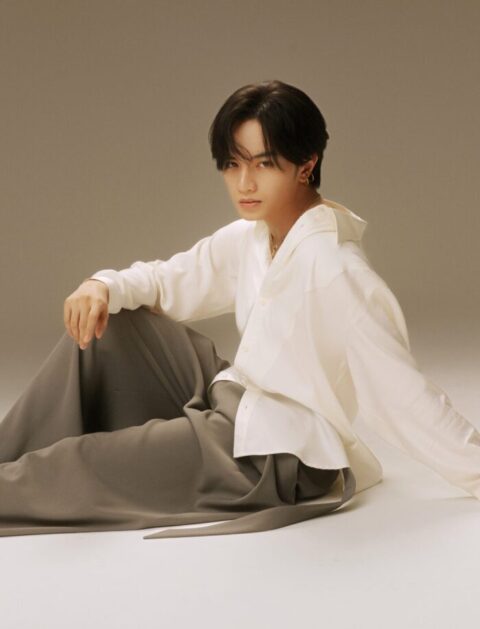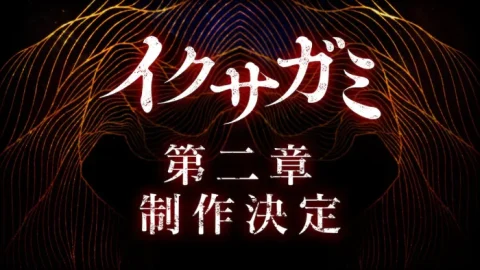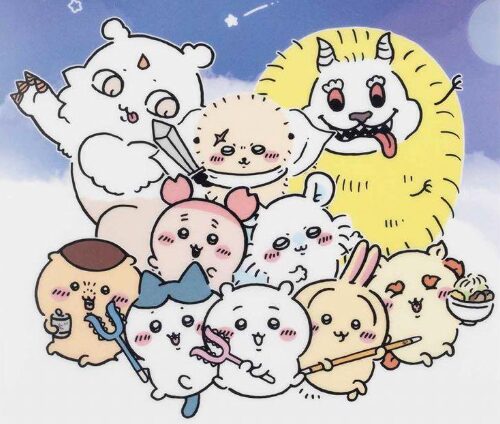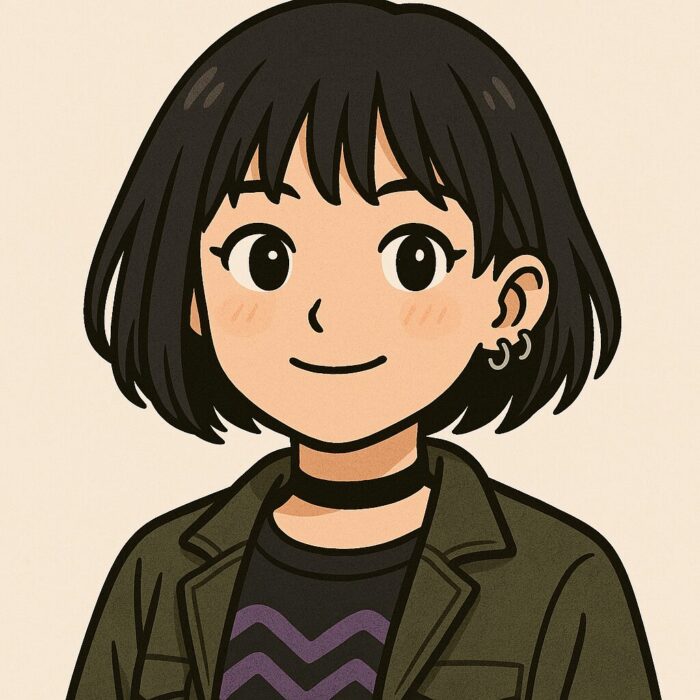令和の育児は「一人では乗り越えられない」から始まる
「育児も家事も仕事も“自分で選んだ道なんだから”全部自分でやるべき」――
そんな自己責任論があたりまえのように口にされるこの時代に、まったく異なるメッセージを放つドラマが誕生しました。
TBS系ドラマ『対岸の家事~これが、私の生きる道!~』は、専業主婦と共働きママという“対極の生き方”をする女性たちの交流を通じて、「共に生きるとはどういうことか?」を静かに、しかし強く問いかけます。
これは、他人を「知らないこと」から始まる誤解と対立を、対話と理解で超えていく物語。
そして、家族や育児の形が多様化した令和という時代そのものを映し出す社会ドラマなのです。
「専業主婦vs共働き」ではなく、“補い合う”という選択肢
主人公・詩穂(多部未華子)は、自ら選んで専業主婦となり、娘の苺を自宅で育てています。
一方、マンションの隣室に暮らす礼子(江口のりこ)は、育児休暇から職場に復帰したばかりのワーキングマザー。
2年間、顔を合わせても口を利くことのなかった2人。しかし、限界寸前だった礼子を詩穂が思わず助けたことから、関係が少しずつ変化しはじめます。
かつて礼子は「今どき専業主婦なんて」と詩穂を見下していましたが、それは自分の選択への不安を覆い隠す防衛本能でもありました。
この物語は、違う立場同士が互いを否定するのではなく、理解し補い合っていく“共助のかたち”を丁寧に描いています。
対話が変える視点──感情の交差点にある気づき
詩穂の言葉や行動は、礼子だけでなく、登場する誰もの“心の深部”に触れます。
たとえば、厚労省勤務で育休中の中谷(ディーン・フジオカ)。
完璧を求める母の価値観に縛られて育ち、失敗が許されない人生を歩んできた彼に対して、詩穂は「母親だからって、許さなくていい」と語ります。
これは、「親だから・子どもだから」という固定観念を超え、個として尊重しあう必要性を突きつける重要な場面です。
詩穂は一見、他者を励ます側の人物に見えますが、実はその過程で彼女自身も深く癒され、変わっていくのです。
「子どもがいない人」も「独身」も──すべての“声”に光を
ドラマの特筆すべき点は、家庭や育児に直接関わる人々だけでなく、社会の多様な立場の声を拾い上げているところにあります。
たとえば、小児科医の妻・晶子(田辺桃子)は、義母や患者からの「子どもはまだ?」という圧力に悩まされています。
詩穂はそんな彼女に「逃げてもいい」と伝え、「まずは自分を大切に」と背中を押します。
さらに、礼子の同僚・今井(松本怜)は独身者ながら、家族同然の愛犬「ココア」と暮らしています。
「ペットのための有給取得」を会社に提案する流れは、人間以外の“家族”の存在までも尊重する世界観を提示しており、多くの視聴者に刺さるエピソードとなりました。
「小さな声を無視しない」ことが生み出す優しさ

作中に登場する絵本『雨のゆくえ』には、「海の上に降る雨」という象徴的なフレーズがあります。
それは、誰にも届かない、誰にも気づかれない声のようなもの。
このドラマはまさに、その“声なき声”を丁寧にすくい上げていきます。
自己責任を振りかざし、他人の苦しみを「選んだ道だから」と切り捨てる風潮の中で、「でも、助ける」「でも、寄り添う」という姿勢を貫く詩穂たちの存在は、とても現代的で、そして希望に満ちた存在なのです。
物語の折り返しが問う、“頼り合うこと”の意味
第5話のラストでは、詩穂に対して「専業主婦はお荷物です」という脅迫状が届き、物語は緊迫感を帯びてきます。
ここからは、今まで詩穂に支えられてきた人々――礼子、中谷、晶子、今井たちが、今度は彼女を支え返す番。
つまり、“助ける”と“助けられる”の循環が描かれることになるのです。
これは「互助・共助なんて理想論」と切り捨てがちな現実社会に対し、「それでも、やるんだ」と訴える強烈なカウンターとも言えます。
まとめ:他者を“知る”ことから、すべてが変わる
『対岸の家事』は、専業主婦やワーキングマザーという枠を超え、現代日本に生きるすべての人に「自分以外の誰かの立場を想像することの大切さ」を問いかけてきます。
一人では子育ても仕事も生き方さえも選べない時代。
でも、誰かを知り、助け合う関係性があれば、人はもっと柔らかく、しなやかに生きられる。
この作品は、そんな可能性をまっすぐに見せてくれる希有なドラマです。
今後の展開にも、ぜひ注目したいところです。
🧩追記:今の日本に“共助”は根付くのか?育児・孤立・自己責任社会を超えるために
現代日本における「共助」は、理念としては美しいものの、実際には制度的・文化的な壁がいくつも存在しています。
たとえば、保育園に空きがない。時短勤務者が肩身を狭くして働いている。男性の育児参加は進んでも、周囲の視線や企業文化が変わらない――。
こうした現実が「共助なんて理想論」と揶揄される背景です。
しかし、『対岸の家事』は、そうした社会の限界を乗り越える“想像力”の力を信じています。
他者の選択や苦悩に目を向け、違いを認め合う勇気。
完璧ではないからこそ、誰かの手を借りることを恐れない強さ。
それらは、制度改革以上に人と人の関係性を豊かにし、孤立の連鎖を断ち切る第一歩になるはずです。
このドラマの登場人物たちのように、まずは小さな声に耳を傾けること。
それこそが、令和の社会に本当に必要な「対岸への橋」なのではないでしょうか。