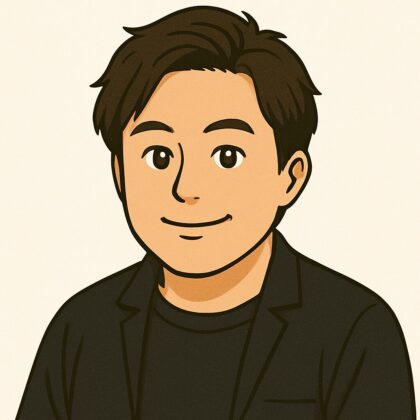静かに胸へ染み込んでくる歌の正体
にしなの「U+」を聴くと、不思議と呼吸がゆっくりになる。音数の少なさでも、派手さでもなく、どこか宙に浮くような“間”が全体を包み込んでいて、聴き手が自分の内側と向き合うための空気がしっかり確保されている。
この曲は2021年6月に公開され、あるテレビCMのために書き下ろされた楽曲だ。にしな自身が語っていた「線引きの薄まり」や「あなたとわたし」という関係性への着目が、作品の芯をつくっている。世の中がコントロールできないスピードで変化する時期に、静かにそっと差し出されたような歌だ。
「U+」が向き合う“線”と“まなざし”

歌詞には、社会が無意識に作ってきた境界線を疑う視点が織り込まれている。
性別や立場、人と人の役割。どうして私たちはそこまできっちり分けてしまうのだろう、と問いかけるようなニュアンスが漂う。
にしなは以前のインタビューで、カテゴライズされることへの息苦しさや、誰かと「あなたと私」として向き合える距離感に関心を寄せていた。そうした考え方は「U+」にも濃く反映されていると考えられる。
楽曲タイトルに置かれた“+”は、単なる記号以上の意味を持つ。あなたと私が並ぶ、その関係性にそっと加えられたプラス。接続の符号でありながら、二人の間に生じる「まだ名前のついていない感情」を預ける場所のようにも感じられる。
歌詞に潜む“追いつく瞬間”の正体
“心が追いつく瞬間”とは、理屈や言葉よりも先に、感覚がふっと定位置に戻るようなあの一瞬のことだろう。行き場の分からない焦りや、社会に用意された役割とのズレが、少しずつ薄れていく瞬間。
歌詞には、時代そのものを俯瞰するような視線がのぞく場面がある。
隠されたものを見つめたい、仕組まれた枠を疑いたい、という思いが象徴的に語られている。その意志は強いが、言葉の投げ方はやさしい。押しつけにならないぎりぎりの場所から、リスナーに問いを委ねているところがにしなの表現らしい。
聴き手は歌を追ううちに、誰かが用意してきた正しさの枠組みではなく、自分自身の輪郭を手で触るような感覚にたどり着く。曲名に込められた“あなたと私”の距離感が、歌詞の中でゆっくりと呼吸を始め、最終的には「自分のいる場所はここでいい」と思える静けさに行き着く。
音の余白がつくり出す、にしなの“呼吸”
「U+」を語るうえで欠かせないのが、音の余白だ。メロディラインは決して複雑ではないのに、耳に残る密度は高い。これは、音を詰めない勇気がもたらす効果だろう。
静まり返るようなパートで、リズムの輪郭がほんの少し曖昧になり、歌声がふと空間に溶ける。その瞬間、言葉と音の境目が曖昧になる。歌詞の“問い”が提示された直後の静けさは、意図的に作られた深呼吸のようで、聴き手の中で未整理な感情が浮き上がる余地をつくってくれる。
にしながもともと持っている“声の質感”は、張り詰めすぎない温度を保っていて、余白の多いサウンドと非常に相性が良い。歌いすぎないことによって、聴き手の想像や経験が入り込むスペースが生まれ、曲との距離がぐっと近くなる。
この曲が日常へ残してくれるもの

「U+」は、聴き終えた瞬間に何か劇的な答えを提示するタイプの曲ではない。むしろ、答えがなくてもいいという前提のまま、“あなたと私”の輪郭をいったんゆるめてくれる作品だ。
忙しない生活の中で、言葉にできない違和感を抱えたまま歩いているとき、ふとこの曲を聴くと、はやる気持ちのスピードがほどけていく。自分のペースを取り戻すのは意外と難しいが、この曲は「いまのままでもちゃんと追いつける」と静かに寄り添ってくる。
日常のどこかでつい置き去りになりかけた心が、そっと元の場所に戻る。その繊細な瞬間を、音楽として丁寧に描いたのが「U+」という楽曲だ。
にしなの表現が“余白”に宿る理由
にしなはデビュー当初から、過度な言語化を避ける傾向がある。ストレートすぎるメッセージではなく、「受け取り方が複数存在する余白」を歌の中に残すアーティストだ。
これは単に抽象的ということではなく、聴き手それぞれが自分の物語を重ねられるよう、意図的にスペースを開けているように感じられる。だからこそ、作品の方向性はシンプルでありながら、聴後感には深みが残る。
「U+」でもその性質はより鮮明だ。問いかける姿勢と、語りすぎない静けさが共存しているため、聴く側の気分や状況によって、まったく違う曲に聞こえる日がある。にしなの楽曲が長く愛される理由のひとつは、ここにあるのかもしれない。
音楽という枠組みを越えて、日々の“答えのない時間”に寄り添うような存在。それがこの曲の魅力であり、にしなの創作の核でもある。
気軽に投稿して下さい♪