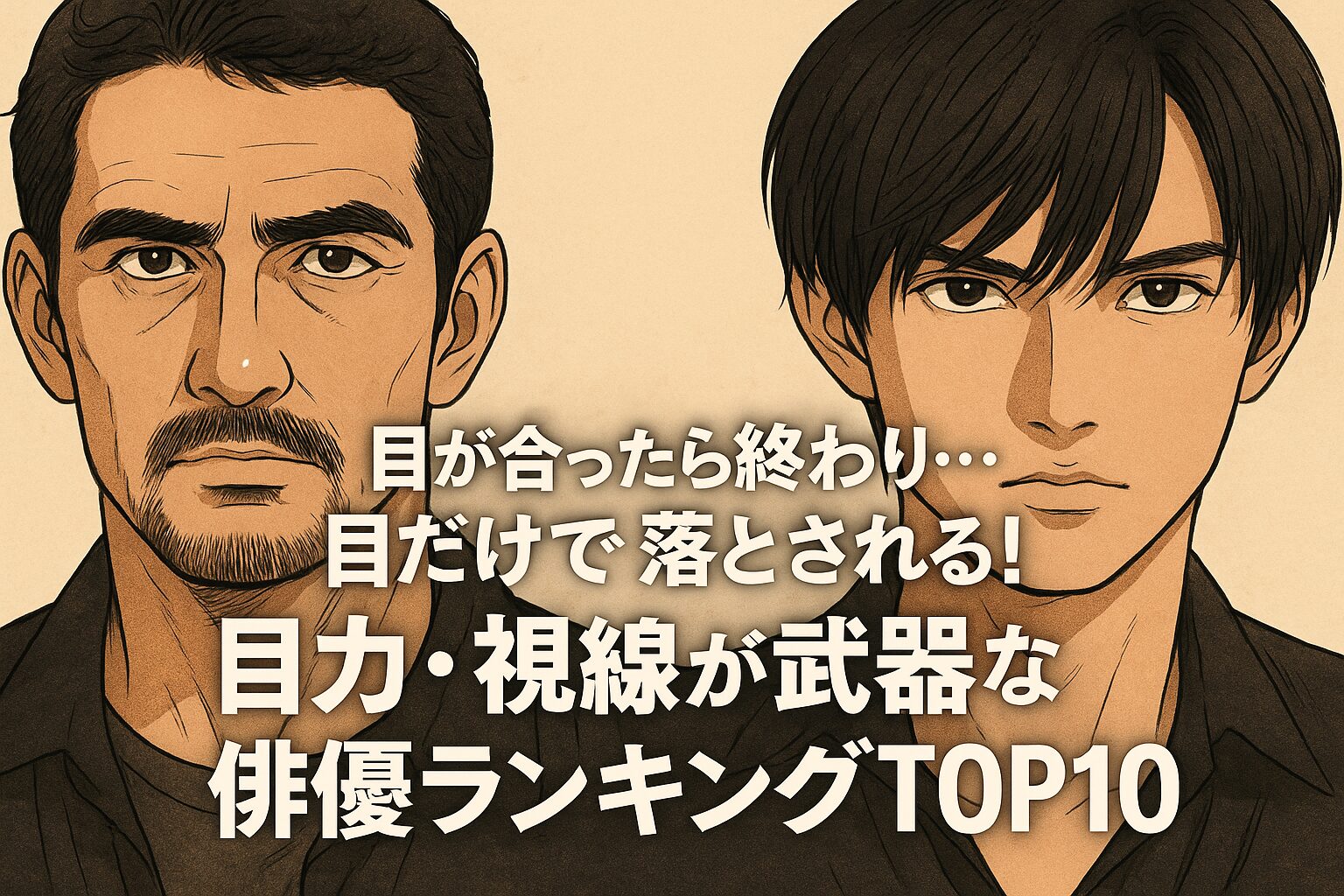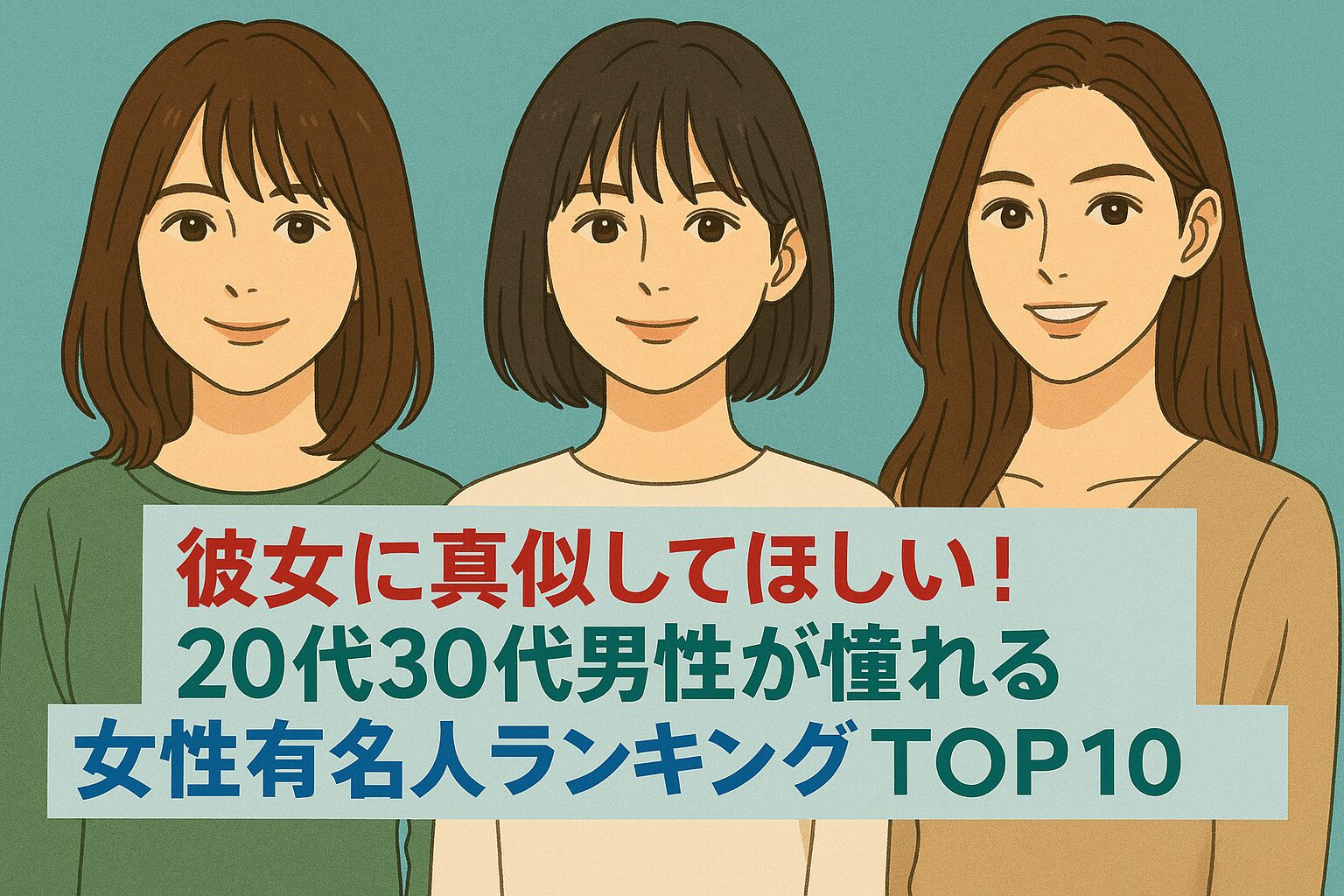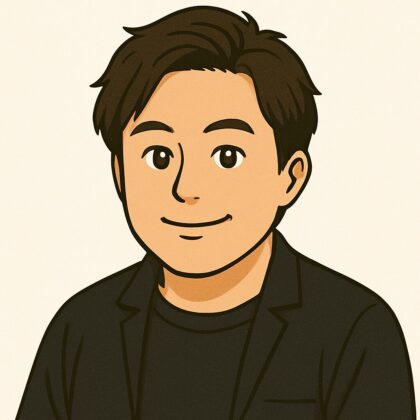ホラーで輝いた“異色の存在感”
Snow Manの渡辺翔太が初主演を務めたホラー映画『事故物件ゾク 恐い間取り』は、ただの恐怖演出にとどまらず、現代の若者像や「共感力の代償」を深く描き出す、意外な心理劇としても注目を集めている。
なぜ、渡辺翔太は“霊を引き寄せる男”という難しい役柄を演じきることができたのか──。
そこには、彼自身の持つ「優しさ」と「繊細さ」、そして現代を生きる人々が抱える共通のテーマが重なっていた。
渡辺翔太が演じたのは「共感体質」の若者
物語の主人公・桑田ヤヒロは、お笑い芸人ではなくタレント志望の青年。夢を追って上京し、「事故物件住みますタレント」として芸能界の世界に足を踏み入れる。
この役がユニークなのは、ヤヒロ自身が“優しすぎるがゆえに霊を引き寄せてしまう”人物として描かれていること。
怪異に巻き込まれていく中で、彼の「共感力の高さ」が裏目に出る構図は、SNSや職場、人間関係において共感疲労を抱える現代人にとって、どこかリアルでもある。
“なぜ渡辺翔太だったのか”に宿る必然性

本作における配役で、渡辺翔太が選ばれた理由は単なる人気だけではない。彼のこれまでのバラエティやライブでの印象とは異なり、繊細で人の空気を読む感受性の強さが、演技にも自然とにじみ出る。
実際に劇中では、強い恐怖よりも、人の心の残留物(思念)に巻き込まれていくような精神的ホラーが展開される。その微細な表情の変化、声の揺らぎ、恐怖と戸惑いのグラデーションを見事に演じ切った渡辺翔太は、まさに“引き寄せられる男”を体現していた。
怪異よりも恐ろしい「感情の置き土産」
映画の中で登場する幽霊たちは、ただの化け物ではなく、生前に抱えた激しい思いや苦悩の残留物として描かれている。そこに共鳴してしまうヤヒロ──つまり渡辺翔太の演じるキャラクターは、ただ怖がるだけでなく、霊たちの哀しみに寄り添おうとしてしまうのだ。
この構図は、まさに“優しさが呪いになる時代”のメタファーでもある。
良かれと思って人の感情を受け取りすぎると、自分が壊れてしまう──そんな現代的な共感疲労が、ホラー映画という枠を超えて、観客の心にじわじわと染み込んでくる。
「みんなに好かれる人」への視点転換
物語後半で明かされるのは、ヤヒロの心の支えとなっていた人物が、勝俣州和(本人役)だったという驚きの展開。
一見、意外なキャスティングだが、彼こそが芸能界において「共感」「バランス」「空気を読む力」で長年生き残ってきた存在であり、ヤヒロ=渡辺翔太と重なるキャラクターとも言える。
派手さやカリスマ性ではなく、“空気に溶け込む力”や“他者を支える力”が評価される存在。
これは、今の時代に必要とされる新しいヒーロー像とも重なっている。
SNS時代の“共感の罠”を描くホラー
本作は、恐怖演出だけでなく、優しさゆえに傷つき、疲弊する若者像にリアルな切り口で迫っている。
- 「人に共感してしまうのがつらい」
- 「他人の感情を無意識に背負ってしまう」
- 「気を使いすぎて疲れる」
こうした感覚に心当たりのある人にとって、ヤヒロの姿は“自分の物語”のようにも映るはずだ。
そしてその役を演じた渡辺翔太もまた、決して押しの強いキャラクターではなく、繊細さと誠実さを大切にしてきた人であることは、ファンの間では広く知られている。
「優しさ」は時に武器になる
『事故物件ゾク 恐い間取り』で渡辺翔太が体現したのは、「優しさのもろさ」だけではない。
共感する力を、最終的には自分の強さに変えていく姿勢こそが、この映画の核心であり、彼の魅力でもある。
“人に寄り添うこと”が時にリスクになる今の時代。
だからこそ、この作品を通して渡辺翔太が示した「優しさの再定義」は、多くの人の胸に刺さるはずだ。
渡辺翔太という人物の“これから”に期待

本作を通して、渡辺翔太が単なるアイドルの枠を超え、演技者としての新たな一面を見せたことは間違いない。
ホラーというジャンルで、恐怖よりも“感情”を軸にした表現に挑んだ彼は、今後の俳優活動においても深い人間描写が求められる作品で存在感を発揮する可能性を強く感じさせた。
Snow Manとしての活動とのギャップに驚かされながらも、彼の内面にある静かな情熱と誠実さが、今回の役柄にこれ以上ないほどマッチしていたのは偶然ではない。
今後、「渡辺翔太」という名前が映画やドラマで語られるたび、観客の中に“感情を映す鏡”としての存在感が強く根づいていくことだろう。