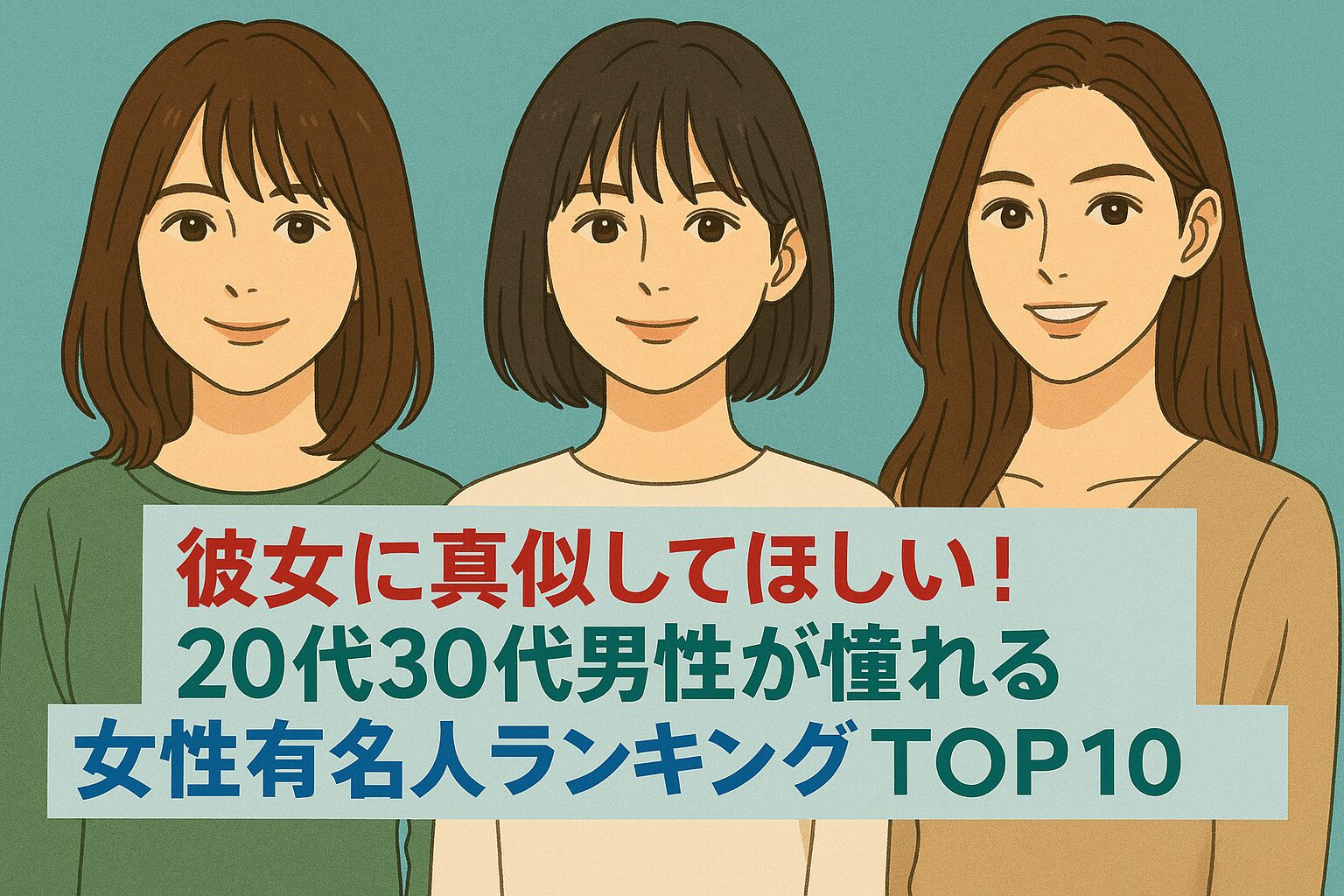心を灯す“煙の向こうの星”――。
黒い煙が立ち込める町の上には、本当に“空”があるのだろうか。
2020年に上演された舞台『えんとつ町のプペル THE STAGE』は、そんな疑問から始まる物語だ。
絵本でおなじみの世界を立体化し、少年ルビッチと“ゴミ人間”プペルの出会いを描いた本作は、多くの観客を涙で包み込んだ。
「泣いた」「勇気をもらった」「まっすぐな気持ちを思い出した」――。
SNSにはそんな感想があふれた。この記事では、観劇者たちの声とともに、この舞台がなぜ“信じる力”を届ける作品として語り継がれているのかを、丁寧に紐解いていく。
舞台『えんとつ町のプペル THE STAGE』とは

原作は、キングコング西野亮廣氏による同名の絵本。
「えんとつ町」に住む少年ルビッチと、ゴミの中から生まれた“ゴミ人間”プペルが、煙に覆われた町の上に“星”を見つけに行く――そんなファンタジーだ。
舞台版は、脚本を西野氏自身が手がけ、演出を児玉明子氏が担当。
主演には萩谷慧悟(7ORDER)と須賀健太が名を連ね、歌・ダンス・映像を融合させたエンターテインメントとして再構築された。
上演は2020年、品川プリンスホテル クラブeX。
入場料は全席指定8,800円(税込)、上演時間は約1時間半。
わずか10名ほどのキャストで織りなされる濃密なステージが話題を呼んだ。
観客を圧倒した「舞台美術」と「映像演出」
開幕と同時に広がるのは、絵本そのままの“えんとつ町”の景色。
立体セットと映像プロジェクションが重なり合い、まるで“飛び出す絵本”の中に入り込んだような感覚を味わえる。
観客の多くが「映像と舞台の融合がすごい」「美術と照明の完成度が異次元」とSNSで絶賛している。
中でも印象的だったのは、ゴミの山や星空を表現する光の演出。
暗闇の中でひときわ輝く“星”が浮かぶ瞬間、客席からは自然と拍手が起こったという。
児玉明子氏による繊細な照明と映像設計が、物語に“命”を与えていた。
泣けた理由①:ルビッチとプペルの“信じる勇気”
ルビッチは、亡き父から教わった「この煙の上には空がある」という言葉を信じ続ける少年。
周囲から“嘘つき”と笑われても、彼は夢を諦めない。
そんな彼の前に現れたのが、ゴミの中から生まれたプペルだった。
二人の友情は、やがて町の偏見をも揺るがしていく。
「信じる心こそが真実を見せてくれる」――。
観客は、二人の行動を通して“希望を信じる力”の大切さを思い出す。
「嘘つき呼ばわりされても、見たものを信じる」というセリフに涙したという声も多かった。
泣けた理由②:音楽とダンスが心を動かす
本作を特別なものにしているもう一つの要素が“音楽”。
西野亮廣が作詞した主題歌「えんとつ町のプペル」が流れるたび、会場の空気が変わる。
舞台ではキャストの生歌とギター演奏が重なり、物語と観客の感情を一体化させる仕掛けが随所にあった。
萩谷慧悟の澄んだ歌声、須賀健太の感情の乗った芝居。
「歌うたび涙が止まらなかった」「ルビッチの表情が忘れられない」との声が相次いだ。
音と動きが“心の震え”そのものを具現化していたのだ。
一方で見えた課題:構成と劇場環境への意見
多くの観客が感動を口にする一方で、構成面への指摘もある。
「セリフが聞き取りづらい」「後方席だと映像が見えにくい」といった声や、
「説明が多くテンポが落ちる場面もあった」という意見も一部で見られた。
ただし、これは“絵本を舞台でどう再現するか”という挑戦の裏返しでもある。
舞台ならではの躍動感を重視した結果、感情表現を優先する演出になったともいえるだろう。
実際に「子どもでも分かる構成で良かった」と肯定的に受け止める観客も少なくなかった。
総評:この舞台が届けた“信じる力”
『えんとつ町のプペル THE STAGE』が多くの人の心を掴んだ理由――
それは“信じることの尊さ”をストレートに描いたからだ。
ルビッチとプペルが見上げた空は、私たちが日常の中で見落としがちな“希望”そのもの。
偏見や不安に覆われた現代社会の中で、「それでも信じたいものがある」と思わせてくれる。
この舞台を観たあと、心のどこかに小さな光が灯る。そんな作品だった。
観劇前に知っておきたいポイント
- 🎟 チケット価格:8,800円(税込・全席指定)
- 🕒 上演時間:およそ1時間30分(休憩なし)
- 👀 おすすめ座席:中央〜前方エリアが最も没入感あり
- 📘 予習ポイント:絵本や映画版をチェックすると感情がより深く伝わる
- 👨👩👧 親子観劇もOK:ファンタジー性が高く、子どもにも分かりやすい構成
“星を信じる”ことが、今を生きる勇気になる
煙の上には、たしかに空がある。
ルビッチとプペルが教えてくれたのは、
「見えなくても信じることが未来を変える」というシンプルな真理だった。
信じることを笑う人がいても、自分の目で見たものを信じる――
この舞台が放ったメッセージは、観客の人生にも静かに響き続けている。
西野亮廣が描く“えんとつ町”という寓話
「えんとつ町」は、煙に覆われた現代社会の縮図だ。
見えない空=希望を失い、他人の夢を笑ってしまう――そんな世界。
プペルは“捨てられたもの”の象徴であり、ルビッチは“それでも信じる人間”の象徴でもある。
西野亮廣は、絵本から映画、そして舞台へと物語を進化させながら、
「信じること」「夢を語る勇気」を繰り返し描いてきた。
演出の児玉明子は、映像と肉体表現を組み合わせることで、そのメッセージを“目に見える形”に変えた。
舞台『えんとつ町のプペル』は、単なる絵本の再現ではない。
観る者一人ひとりに問いかける、“現代の寓話”そのものだ。
「信じる力」とは、誰かを励ますことでも、自分の弱さを受け入れることでもある。
この作品は、そのどちらもそっと肯定してくれる。