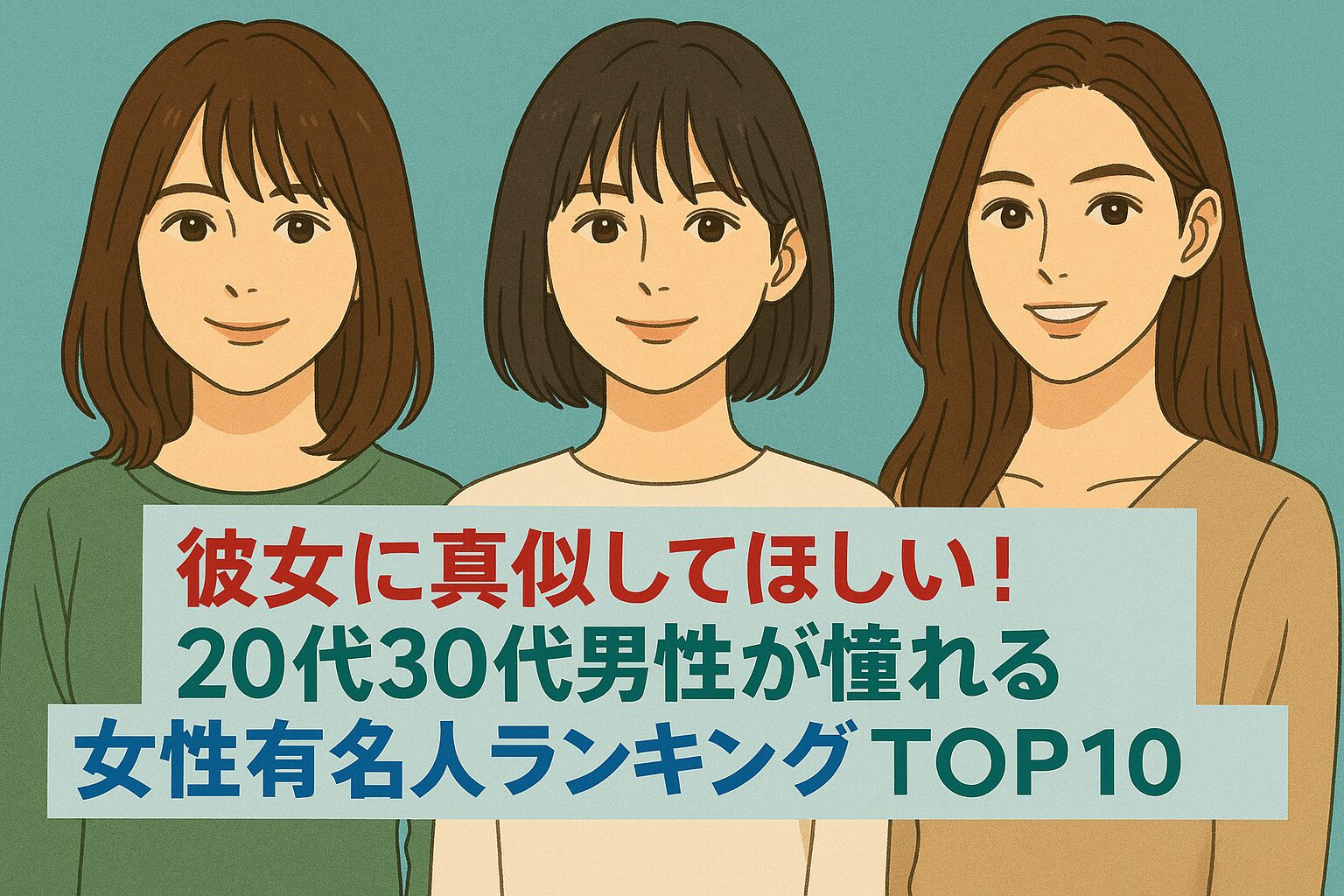派手さよりも心に響く舞台がある
2025年9月、日生劇場で幕を開けたミュージカル『Once』。
主演はSixTONESの京本大我。2007年に公開された映画版はアカデミー賞歌曲賞を受賞し、その後2011年に舞台化されるとトニー賞8部門を制覇。いまや世界中で愛される名作となったこの物語が、2025年の日本版で新たな息吹を得ました。
この作品の最大の特徴は、ミュージカルと銘打ちながらも「ショー的な派手さ」をあえて排した点にあります。舞台にあるのは、シンプルな装置と生演奏を奏でる俳優たち。そして、観客を包み込むのは「音楽と人間の関係性」そのものです。開幕直後からSNSや観劇ブログに感想が溢れたのも納得の仕上がりでした。
作品背景:映画から舞台へ、そして日本へ

『Once』の原作は、アイルランド・ダブリンの街角で撮影された小規模映画『ダブリンの街角で(Once)』。製作費はわずか15万ユーロという低予算ながら、主演グレン・ハンサードとマルケタ・イルグロヴァの素朴な演技と、映画全編に流れる生演奏の温かさで、口コミから世界的ヒットに成長しました。
特に挿入歌「Falling Slowly」はアカデミー賞歌曲賞を受賞。観客の心に「音楽が人を救う」というテーマを強く刻み込みました。
その後、2011年に舞台版が誕生。ブロードウェイで開幕すると、トニー賞で8部門を制覇し、「小さな物語でも世界を震わせる」ことを証明しました。舞台の大きな特徴は、キャスト自身が舞台上で楽器を演奏し、物語を動かしていく構造。これが「観客が音楽の現場に居合わせているような臨場感」を生み出し、世界中で上演され続けています。
日本では過去にも上演歴がありましたが、今回の2025年版は東宝が手がけ、京本大我を主演に迎えることで大きな注目を集めています。
京本大我という主演俳優の現在地
SixTONESのメンバーとして知られる京本大我は、近年ミュージカル界でも頭角を現してきました。『エリザベート』のルドルフ役をはじめ、『ニュージーズ』など大作に出演し、繊細な感情表現と伸びやかな歌声で着実に評価を高めています。
そして2025年、30代を迎えて最初の舞台として選んだのが『Once』。大役を背負うにふさわしいタイミングでした。観客の声を集めても、最も多く語られるのはやはり「京本大我の歌声」。
「ギターを弾きながら歌い出す瞬間に、すべてを持っていかれた」
「舞台というより、彼の人生の一部を見ているようだった」
SNSや観劇レビューでこうしたコメントが相次ぎました。これまでの大作ミュージカルとは異なり、『Once』はほぼ主演俳優の存在感に依存する構造。京本が見せる“素”に近い表現が、観客に強い余韻を残しています。
共演者とアンサンブルが生む厚み
今回の日本版でガール役を演じるのはシンガーのsara。透き通るような声質と芯のある表現力で、観客を自然と物語へ導いていました。京本とのデュエット「Falling Slowly」では、客席の空気が一変し、「二人の声が重なる瞬間に涙がこぼれた」と感想を語る人が多かったのも頷けます。
ベテラン勢の存在感も大きな支えになっています。斉藤由貴は柔らかさと深みのある演技で舞台全体に温かさを加え、鶴見辰吾は重厚な存在感で物語を引き締めました。さらに新井海人ら若手も、自ら楽器を演奏しながら参加することで、舞台全体がひとつのバンドのように響き合います。
「キャスト全員の呼吸が合っていて、アンサンブル全体がひとつの楽曲のように感じた」
という声もあり、単なる俳優の共演を超えた一体感が感じられました。
演出の特徴:削ぎ落とされた舞台美学
『Once』の舞台セットは驚くほどシンプルです。背景にはダブリンの街を思わせる小さな酒場のような空間があり、椅子や楽器が置かれているだけ。シーン転換も最小限で、役者たちが楽器を奏でながら舞台を行き来することで物語が流れていきます。
ある観客は「舞台全体がひとつの楽器のようだった」と評しました。装置に頼らない分、俳優の演奏や歌声が直接観客の感覚を揺さぶるのです。
照明も華美ではなく、温かな光で人と人との距離感を浮かび上がらせます。そのため、「まるで劇場全体が酒場になったような感覚」や「自分もダブリンの片隅で音楽を聴いているような錯覚」に陥る観客も少なくありませんでした。
音楽の力:物語と一体化する楽曲
『Once』における音楽は、単なる挿入歌ではなく物語そのものです。ブロードウェイ版でも指摘された通り、楽曲は独立したショーナンバーとして披露されるのではなく、登場人物の感情の流れに溶け込むように演奏されます。
特に「Falling Slowly」は、日本語歌詞であっても違和感なく観客の心を掴みました。SNSには「日本語でも鳥肌が立った」「意味がダイレクトに伝わり、胸が震えた」といった感想が溢れています。
また、マンドリンやヴァイオリンのトレモロが場面を彩る瞬間には、「音楽そのものが舞台を動かしている」という感覚を味わえます。従来の“ナンバーごとに拍手が起こる”タイプのミュージカルとは異なり、観客が呼吸を忘れるほど物語と音楽が融合していました。
ストーリーの受け止め方と賛否
物語は「人生の再生と別れ」がテーマです。傷を抱えた人々が音楽を通して一瞬の輝きを分かち合い、やがてそれぞれの人生に戻っていく。観客の多くはこの普遍的なテーマに強く心を揺さぶられました。
「人生は続いていくんだと前を向けた」
「胸が苦しくなるほど美しい物語だった」
といった声がある一方で、ラストシーンについては意見が分かれます。「なぜ結ばれないのか」と戸惑う観客もいれば、「あの切なさこそがOnceの真髄」と受け止める観客も。解釈が分かれる余白こそが、この作品を何度も観たくなる理由のひとつでしょう。
観客層の広がりと多様な感想
今回の公演では、京本大我のファンだけでなく、普段からミュージカルを観ている層や、映画版からのファンまで幅広い観客が訪れています。
京本のファンは「アイドルとしての彼とは全く違う顔に驚いた」と語り、ミュージカルファンは「東宝が挑戦した新しい形の舞台」と評価。さらに、「初めて舞台を観たが、想像以上に心に響いた」と感想を残す観客も多く、新しい観劇層を取り込むことに成功している印象です。
映画版との比較
映画版『Once』は、ドキュメンタリーのような質感で撮られたこともあり、親密さとリアリティが特徴的でした。一方で舞台版は、観客と同じ空間で音楽が生まれる瞬間を体感できるという大きな違いがあります。
映画では「切り取られた一瞬」を観る感覚でしたが、舞台では「自分がその場に居合わせている感覚」が強まります。日本版ではこれがさらに強調され、観客からは「まるで自分もダブリンの酒場に座っているようだった」という声も聞かれました。
静かな衝撃と再演への期待
『Once』2025日本公演は、京本大我の表現力、共演者のアンサンブル、そして音楽が物語そのものとなる演出によって、観客に深い余韻を残しました。派手さはなくとも、胸の奥に長く響き続ける。まさに「静かな衝撃」と呼ぶべき舞台です。
チケットは入手困難で、大阪公演を控える今、さらに口コミが広がることは間違いありません。音楽ファンにもミュージカルファンにも、そして人生に小さな再生を求めるすべての人に勧めたい舞台です。
なぜ『Once』は日本の観客に刺さるのか
『Once』がここまで支持される理由は、日本社会の現状とも重なります。仕事や人間関係の中で疲れを抱えながらも日常を生きる私たちに、「一瞬の出会いが人生を変える」という物語は強い共感を呼ぶのです。
また、派手な演出が続く日本の商業ミュージカルにおいて、『Once』のシンプルさは逆に新鮮に映ります。東宝がこの作品を手がけたこと自体が挑戦であり、日本のミュージカル界の幅を広げる試みとも言えるでしょう。
そして何より、京本大我が主演を務めることによって、普段は舞台に足を運ばない層が劇場に来るきっかけとなり、観劇人口の拡大にもつながっています。彼のような表現者が立つことで、作品が持つ「音楽で人と人をつなぐ」というテーマが現実の観劇体験として体現されているのです。
気軽に何でもコメントしてね🎵
気軽に投稿して下さい♪